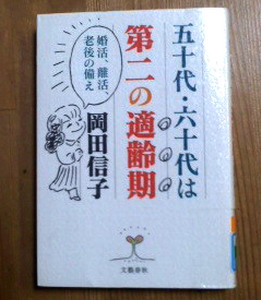アーカイブ: 2014年9月
2014/09/29
小学校の同窓会 (1928)
昭和29年卒業の 同窓会が開かれた。
その頃は ひとクラス50名以上。
今回は4クラス合同の同窓会で 出席は74名。
学校は瀬戸物の町の中心部にあり、
家業も瀬戸物に関係する家の子が多かったようだ。
わたし達も本物の茶わんで
(規格外品。瀬戸のことばでペケと言った)
ママゴトをやって遊んだものです。

校歌にも、
「里のほまれは陶(すえ)の業(わざ) 祖先のいさを承け継ぎて
いよよ高く 瀬戸の名を 挙げん 吾等の責重し」
と あるように、
今も市中の仕事として 瀬戸物は盛んである。
50年以上も会ったことのない同級生。
会場で出会ったばかりのときは気が付かなかったが、
しばらくして笑顔を見たら
小学生の顔がぱ~っと浮かび 思い出した。
同じ時代を過ごした友は ほんとうに良いものですネ。

*****
2014/09/27
ろくろ日和 (1927)
秋晴れ 最高気温28℃ 湿度45%。
孫は小学校の運動会。
わたしは朝からろくろで湯呑みを挽く(7個)
よく乾燥して 昼からはすぐに削る。

その間に 家庭菜園のゴーヤを収穫する。
ここ2~3日好天気なので きょうも10個も採れた。
かき揚げ、ゴーヤチャンプル、お浸し、野菜炒め・・と
とても食べきれないので、あいこちに貰ってもらった。

読書もしたいし、夕御飯も作らねば・・
あ~っという間に ろくろ日和も夜になってしまう。

*****
2014/09/26
よりみち探偵団 (1925)
よりみち探偵団の 集まりの日
まだ暑いし・・
いままで歩いたところの おさらいと、
どのようにまとめていくか、を話し合った。
犬山城から木曽川に沿っては、
舟大工、漁業組合といった跡がある。
水運、材木という点からも いろいろなものが見えてくる。

車ではよく通るが、すこし脇道にそれて歩くと、
小さな、この地ならではの発見がある。
よりみちの特徴は、こうした すこしの変化も見逃さない。
調べて、不便でも 街の豊かな時代に思いを馳せることができれば楽しい。

*****
2014/09/23
田園風景の中のカフェ 「月田」 (1924)

本で見る以前から行ってみたいと思っていたカフェ。
家から車で一時間近くかかるので、
なかなか行く機会がなかった。

和風建築で、室内のインテリアも調度品も、
わたし好みのものがいっぱい。
李朝箪笥(ラデン入り)、小鹿田焼の壺、骨董の器の数々。
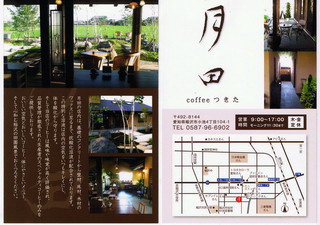
帰りがけにオーナーのご主人と話す機会があった。
この建物は
天井、柱、壁材、床材から木材に塗るワックスに至るまで、
抗酸化溶液が配合されたもので仕上げられているそうだ。
店内の空気はいつもきれいに、酸化から守る為だとか。
お店が「とても気に入った」と伝えたら、
「コーヒーを飲むなら
おいしくて雰囲気の良いお店がよい」のでね・・と。

【写真下】お茶の間通信社刊・地域情報誌「Egg」No.113号から
*****
2014/09/21
『 五十代・六十代は第二の適齢期 』 岡田信子著 (1923)
岡田信子・著 『 五十代・六十代は第二の適齢期 』
~ 婚活・離活、老後の備え ~
中高年の婚活の話が主だが、
老夫婦の老後の備えや
ボケないうちに二人がなすべき重要事項や、
片づけられない人のための
Q&Aの項は参考になりました。
著者はわたしより10歳年長なので、
わたしは「まだ いいか」と思うが・・
人は(特殊な例外を除き)
みんな 一人で生まれ 一人で死ぬのである
ということ。
一方で もう今から意識しておかねばね。
中高年の方々 一度読んでおかれると いいですよ。
【写真】 岡田信子・著 『 五十代・六十代は第二の適齢期 』 ~ 婚活・離活、老後の備え ~ 2011.6.10.第一刷 @1333e
******
2014/09/20
明治カルチャー講座 (1922)

今年も市民大学のカルチャー講座が始まった。
第1回目は博物館明治村 建築担当係長の石川新太郎先生。
「保存修理から見る 明治村の建物」
~ 西園寺公望邸「坐漁荘」の魅力 ~
明治から大正にかけて建てられた時と同じような材料や
造り方を求めて、修復工事をするのは、
いかに大変なのかがわかりました。
また 襖(ふすま)紙一枚でも、どんなにか苦労して再現するか、時間も費用もかかり、大変な仕事ですね。

きょうの明治村は あまり良い天気ではなかったが、
人出は多かった。
最近はNHKの朝ドラのロケ撮影場所となっている影響もあり、
ずいぶん賑わっているようです。

*****
2014/09/19
鳴海てがし神社 (1921)

家から近く(車で5分)だが、訪ね入ったことのない神社。
・・鳴海てがし(杻)神社。
買い物帰りに ちょっとよりみちした。
祭神がどんな人かもわからないし、わたしは関心がうすいが、
ヒノキ、ハナノキ、クロガネモチなど境内の樹木が立派だ・・

とくにベイマツ(アメリカマツ)。
葉が三本、四本の葉からなり、三つ葉のマツは珍種です。
わが実家は材木商で、マツをよく見ていたこともあり、
大きな樹を見ていると 気持ちがいい。

この神社の境内の前に、弁天様を祀った弁天堂がある。
弁天堂の内池の脇には、お金を洗えるようになっている。
ここの湧水で洗ったお金を持っていると
何倍にもなると言われているそうです。

ざるまで備えられていて、折角だから155円洗ってきた。
・・おもしろいですね。

近くの今昔物語をたどるのも 時には よいものです。

*****
2014/09/17
窯神(かまがみ)神社 (1920)

瀬戸市に 用事があり、
窯業を営んでいる、弟の友人を訪ねた。
わたしが出た小学校にほど近く、
このあたりへは何十年振りか。
あたりの町の様子はすっかり変わっていた。
このご主人と わたしは同じ小学校出身なので、
話しがはずんだ。

家業の焼き物(器)を褒めたら、
なんと ひとつ下さった(ラッキー!)

帰り道 急坂をさらに上の方へ行くと、
磁祖・加藤民吉をまつる窯神神社があり、お詣りした。

この神社は、小学生のころ写生会をしたり、
放課後に遊んだりした・・
毎年9月の第二土曜日・日曜日が 例祭日で、
この日 「秋のせとものまつり」が街中で行われる。

※ 「春の せとものまつり」は、瀬戸の産土神を祀る深川神社の例祭日(4月第3日曜日)に合わせて 街中で行われる。深川神社には陶祖・加藤景正の手による陶製狛犬が在る。
*****
2014/09/16
特別展・・加藤卓男展 (1919)
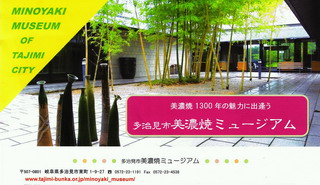
第10回 国際陶磁器フェステイバル美濃 '14 協賛で
特別展 加藤卓男展 ~オリエントと美濃を結んだ生涯~
が開かれている。
場所は セラミックパークMINOから 車で5分ほどとなりの、
多治見市美濃焼ミュージアム (多治見市東町1-9-27)
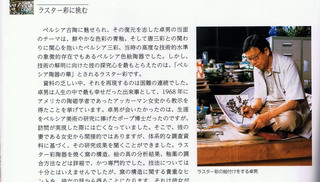
中東/オリエントで出合ったペルシャ陶に 強い関心を抱き、
ラスター彩、ペルシャンブルーの再現と、
独自の作風を作り出した 加藤卓男氏。
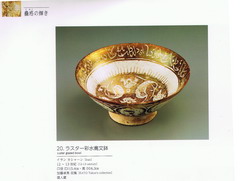
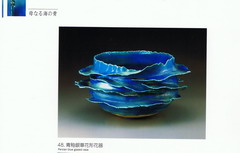
わたしは多治見市 市之倉町の幸兵衛窯を何度も訪れた。
作品も その都度 拝見している。
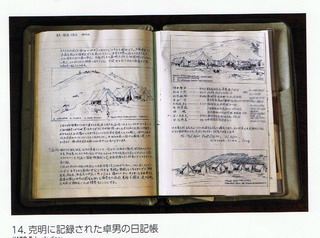
きょうの特別展では 展示卓のガラス越しに
卓男氏が記した日記の数々を読んだり、
特別展の図録も求めて読み、さらに驚いた。
地図や見取り図の絵も 細かく描かれているし
日々の書き留め文章も克明に書かれている。
几帳面で、努力の上に努力を重ねられ
あのような作品の数々が生まれたことを知った。
天賦の才能のうえに、オリエントとの出合いから
熱い砂漠への思いに 何度も中近東に出かけ、
苦労されたことの意味の大きさを感じた。
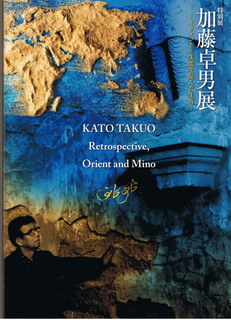
<写真は いずれも買い求めた図録から転載しました。>
*****
2014/09/15
国際陶磁器フェスチバル美濃 ’14 (1918)

世界最大級の 陶磁器の祭典が、3年に一度開かれる。
・・・ 国際陶磁器フェスチバル美濃 ’14
ことしも9月12日から10月19日まで
セラミックパークMINO(多治見市東町4-2-5)で開かれている。
きょうは4日目だったが すごい混雑ぶりでした。

イタリア、中国、韓国、台湾の作家さん・・
タイトルと作品を見て、平凡なわたしには、
首をかしげたくなる作品もあった。
が、アーテイストは
あのようなやわらかな考えとイメージがなければ
いけないのでしょうね
わたしも作陶するとき思い出してヒントにしたいと思った。
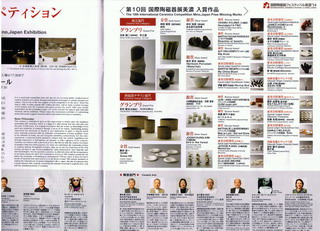
昨日も作文教室の先生がおっしゃったこと・・
よく調べて やわらかな やわらかな頭で考えて
文を作らなければいけない・・
何事もすべてそうですね。
いくつになっても 学ぶこと多し・・です。
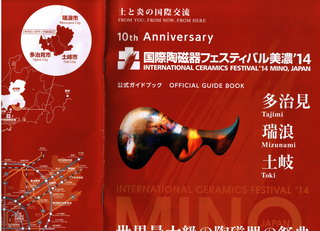
*****
2014/09/14
9月の作文教室 (1917)
9月の作文教室
朝 8時半に家を出る。 2名おやすみとのこと。
「本当なんだ」というタイトルで書かれた男性(ひと).
奥さんを交通事故で亡くして以来、
何かをしているときに ふと誰も居ないことに気付く。
・・「本当に居なくなった」と気付く。
そんな場面をいくつか思い出して綴ったエッセイ。
目の前でこの作文を読まれると、文章の上手、下手よりも
この男性(ひと)の心情を思って 胸が痛い。
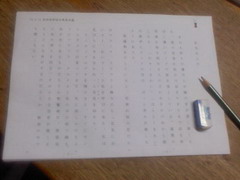
童話のNさんの文も とってもよかった。
毎回、前回の作文が(赤筆で)直されて、励みになる。
先生 ありがとうございます。

*****
2014/09/13
学生時代の友と食事会 (1916)

高校時代の友 数人で おしゃべりと食事の会
きょうの場所は名古屋駅近くのミッドランドスクエア。
名古屋市内の女子高だったので、近隣に住む人が多く、
ここ名古屋は全員がなじみ深い。
このメンバーはみんな健康なこともあり、
病気の話はあまり出ない。
が、年齢も進み、最近は認知症の話は出る。
中学・高校時代の話をしながら、
笑い転げて 過ごすひとときは、
いくつになっても いいものですね。
次回は12月に忘年会を約束して・・

*****
2014/09/12
『 歩いて行く二人 』 岸恵子 吉永小百合 (1915)

『 歩いて行く二人 』著者・岸 恵子 吉永小百合
日本人なら誰でも知っている二人の対談と写真集。
わたしは岸恵子さんが好きで、
書かれた小説やエッセイはほとんど読んでいる。
映画も何本かは観ている。
一番好きなのは ルポルタージュエッセイ。
『 ベラルーシの林檎 』『 私の人生アラカルト 』
小説『 わりなき恋 』など。
対談の内容は驚くような珍しい話はなかった。
たくさんの写真はきれいだった。
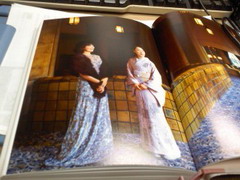
いつか「徹子の部屋」に出演中、 徹子さんが
「みなさん どうして老いてもきれいなの」と驚かれます、
と言われた。
岸恵子さんが
「あら 皆さんは どうして年寄りになってしまうの」
と答えていらしたのが 忘れなれない。
昭和7年生まれ、82歳。
信じられない女性(ひと)。
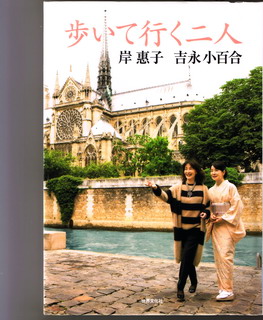
【写真】 『 歩いて行く二人 』 世界文化社・刊
著者:岸 恵子 吉永小百合
2014.7.15.初版第1刷発行 @1800e
*****
2014/09/08
カーネーション (1914)
NHKBSプレミアムで
朝ドラ・カーネーションの再放送をやっていた。
ドラマは終わりに近づき、
主人公は歳をとって女優さんが代わっていた。
主人公と 5~6人の男性の老人が食事をしているシーン。
「男はんは 独りでご飯を食べてはいけない」・・
ということで、主人公は
時々こうやってにぎやかに夕ご飯を食べる機会を作るという。
わたしは このひと言に考えさせられた。
わたしの年齢になると ボチボチおひとりさまになる。
「独りで食べる」男性も、
自分から「楽しい食事」をする努力をしたらよいのになあ。
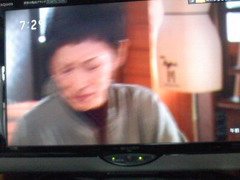
*****
2014/09/07
社寺めぐりとなりました (1913)
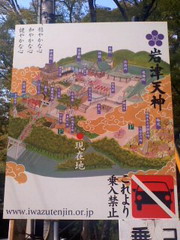
岡崎での用事が早く終わったので、
近くの岩津天満宮(岩津天神)に行った。
ここは学問の守り神 病除けとして有名だが、
訪ねたのは 初めてだった。

天神様(菅原道真公)が好きな花、
観梅の名所として 梅林が多くある。
強い陽ざしに
境内にも梅干しがいっぱい干してあった。
今は願いごとも特にあるわけではないが、
しずかに参拝してきた。

帰り道、家人が、いま新聞小説に出てくるので、
定光寺も訪ねてみようという。定光寺本堂は重要文化財。
わたしは この前の通りを何度も通るが、
境内までは初めて行った。

山の上にあり、参道の階段が165段ほど。
休み休みではあったが、暑くてしんどかった。
登りきったところで、山門から車が見えた。
10年くらい前から車で登れる坂道ができたとか。
皆さん 車で登って来る人がほとんどだった。
でも、参道を登ってくる者はご利益がありますよ、と言われた。
きょうはなんだか
わたしにはめずらしい寺社巡りの日であった。

*****
2014/09/06
きょうは ロクロ日和 (1912)
粘土を買ってから、出かける日がつづき、
なかなかロクロに向かえなかった。
お天気も どうにか晴れている。
家族も出かけて ひとりなので朝から陶芸。
ロクロを挽いてしまい、
削りに入るには時間がかかるので
そのあいだは読書・・

『 吾輩ハ猫ニナル 』 横山悠太・著 講談社・刊
1981年生まれというから30代の若い作家。
大型新人のデビュー作という。
日中混血の青年が見た、日中の文化論がおもしろい。
中国語でコンビニを、著者は「便利店」と表記する。
おにぎりは「飯団」、
パソコンゲームソフトは「電脳遊戯軟件」
ルビがふってあるので 読みやすい。
湿度が高くて、読み終わっても削れるほどには
乾いていなかった・・
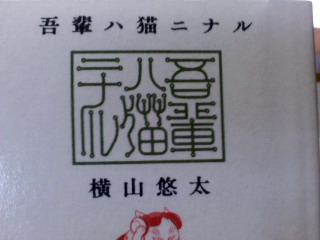
【写真・部分】 横山悠太・著 『 吾輩ハ猫ニナル 』
2014.7.15.第一刷発行 講談社・刊 @1200e
****
2014/09/01
絵手紙展 (1911)
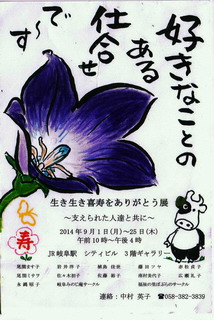
作文教室の仲間である方・Nさんが、
「生き生き喜寿をありがとう展」を
JR岐阜駅シティビル3階で 開かれている。
9月1日~9月25日(木)まで(入場無料)

友人で絵手紙を教えているひとを誘って出かけ、
見せていただきました。

大きな和紙に描かれた絵手紙の数々、
どれもNさんの個性が光っていました。

日ごろ作文教室の文章でも飾らないけれど、
知性的な文面に感心してしまいます。
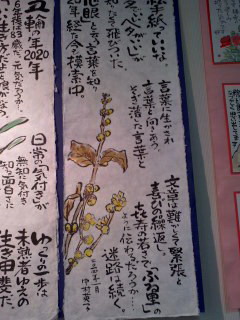
よく「一生懸命 言葉を探しています」
と言われるだけあり、
絵と文章が絶妙にマッチして見応えがあった。
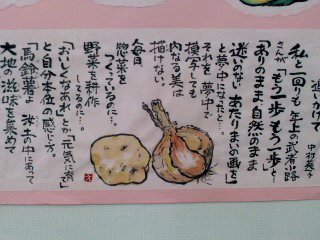
一緒した友人も
「参考になったわ・・」と喜んでいました。

久しぶりに電車で岐阜駅まで行った・・
昼ご飯や 買い物を楽しみました。
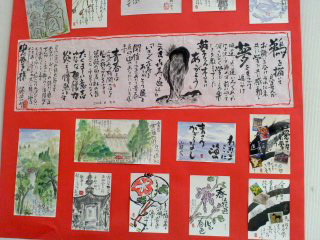
※ 「生き生き喜寿をありがとう展」
~支えられた人達と共に~
2014.9.1.(月)~9月25日(木)
午前10時~午後4時
JR岐阜駅 シティビル 3階ギャラリー
*********