2012/12/20
ソウルの旅 (1)(北村東洋文化博物館) (1693)

17日に出発。今回はまったくフリーの、4日間の旅。
仁川(インチョン)空港からホテルまでも、自分たちで行く。
最高気温もマイナス4度などと表示してある・・。
それでもホテルに着くと、明洞を散策して楽しむ。

18日 朝早く歩いていると、
お店の方が「寒いヨ。いまマイナス9度」と教えてくれる。
韓国人の友人Cさんが迎えに来て、
金浦空港近くの自宅へ連れて行ってくださる。
元気で 再会を喜び合う・・。
昼食はサムゲタンで 温まる。
ホテルに帰ってから、また明洞(ミョンドン)に出かけ、
ソウルらしい にぎやかな店々を のぞく・・。

19日は盛りだくさんの予定を立てている。

朝一番は三清洞(サンチョンドン)で、北村東洋文化博物館へ。
(東京の青山を真似て街づくりをしたという、おしゃれなところ)

「北村(プッチョン)東洋文化博物館」へ・・

季陶ギャラリーを観て、急いで仁寺洞へ。
同行の普茶料理の先生のために選んだ精進料理食べに行く。
昨日予約して、場所は人に尋ねながら探した店「パルコンヤン」へ行く。
(つづく)
2012/12/16
明治村学講座 (帝国ホテル中央玄関) (1692)

明治村学講座。 最後の講座は 帝国ホテルの特別見学会。
この一週間は 寒さが厳しかった。
きょうは晴天。陽だまりに居るとあたたかくて、帝国ホテル前庭越しに入鹿池を見ると「日本の風景 ここにあり」という情景。

20名ぐらいづつ3つの班に分かれて「特別見学」シールを胸に貼り、学芸員について帝国ホテルの内部を見学した。

ここへは何度も来ているが、こうして説明を受けて見ると、
この建物がこんなにも手のこんだものだった・・。
帝国ホテル中央玄関は、
日本の宝物のひとつだ ということが よくわかった。

・・明日からは 友人とふたりで韓国へ3泊4日で行ってきます。
韓国の友だちCさんに先日電話をしたら「また会えるの。うれしいなあ」と言っていただき、わたしもたのしみです。
ソウルの国立中央博物館の日本館ボランテイアのTさんも、わたしたちのために わざわざ公休日に出てきてくださるので、これもうれしい限りです。
**********
2012/12/10
『 雨の日の手紙 』 秋山ちえ子 (1691)
秋山ちえ子・著 『 雨の日の手紙 』 文春文庫
先月の文章教室で、
先生が何冊かの愛読書を持ってこられた。
この本には、秋山さんと串田孫一さんとのことが書かれてあることを話されました。
(串田孫一さんは 哲学者で大学の先生でありエッセイスト)
わたしは串田孫一著の本が好きで、若いころ何冊も読んでいたので、この本をぜひ読みたいと思った。
先生に尋ねると、
もう20年近くも前の発行の本だから、現在は販売されていないので、お貸しします、と言ってくださった。
秋山ちえ子さんは、TBSラジオの「秋山ちえ子の談話室」でよく聴いていた。
この本の内容は、いくつものエッセイがあつめられている。
どれも落ち着いた名文章で 読んでいて心がなごむ。
先生が長い間、傍らに置いてときどき読んでおられる姿が思い浮かんでくるようです。

【写真】 秋山ちえ子・著 『 雨の日の手紙 』 文春文庫
1993年1月10日 第1刷発行 文芸春秋・刊 @388e
2012/12/09
冬の景色 (1690)
今朝は最低気温0℃。
上天気で 8時ごろウオーキングに出かけた。
五条川の自然歩道を歩いていくと、オシドリがいた。
写真を撮っていたら、顔見知りの男性が---さっきカワセミが居たよ、と話しかけられた。
もう少し上のほうへ行くと、オシドリもたくさん居るらしい。
紅葉も散り、冬景色の川。
すがすがしい気持ちでしたが、
うちに近づくと、選挙カーの大きな声と 手を振られた。
(わたししか居なかったので)いっぺんに気分を損なわれた・・。

2012/12/04
ガーデニング (1689)

わたしの普茶料理の先生は、もともとガーデニングがお得意。
多くの場で指導され、活躍されいる。
11月末に「ジャパンフラワーオープンinしずおか」のコンテナガーデニング部門で優秀賞をもらわれた。
知事からトロフィーと賞状。副賞に海外旅行券もらわれた。
電話で話されたときは とてもうれしそうでした。
本当におめでとう。
今回 お宅に伺って 見せていただいた。
土のブレンドと花との相性など、いろいろな面からきびしく審査されたので、選ばれても信じられなかったと話される。
インテリアや 料理の盛り付けにも、持ち前の感性が光り、
視野が広い方なので、選ばれて良かったと、
わたしは心から喜んであげられた。
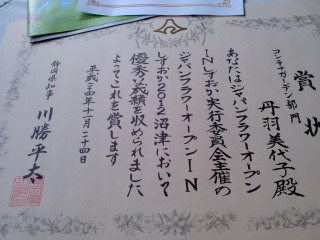
市民大学・明治村学講座 (1688)

市民大学:明治村学講座。
本日の講師は博物館明治村建築担当の石川新太郎先生。
昭和40年(1965)に開園。 ことしで47年。
明治村ができるキッカケは、あの「鹿鳴館」が昭和15年(1940)に解体されてしまったことにある。
これを惜しんだ建築家谷口吉郎さんと、同級生の土川元夫さん(名鉄副社長)とが、
解体されてしまう歴史的建造物の移築保存を発起した。
鹿鳴館は 築57年目で解体。
帝国ホテル中央玄関は 45年目で解体移築。
・・ということは、だいたい50年でリセットするということ。
西園寺公望公別邸「坐漁荘」が 現在修理中。
数寄屋造りの別邸は、これほどの材料が!?というものを使っているという。
トイレにしても、これ何?!というほど、部材に凝ってある。
扉にはところどころに黒柿が使われ、ふすま貼りには京都龍村織物が使われている。
・・修理にかかる費用も大変だろう。
来年度中に修理工事は出来上がりそうとのこと。
ぜひ見に行きたい。
明治村には いま68点 64棟がある。うち重要文化財10棟。
この修理修繕、維持管理は 大変なのだ。
この先生の話しを聞きながら、家の近くに(車で10分)こんなすごいところがあると改めて感じた。

あいにくお天気が悪く、とても寒くて観光客も少なめ。
いつも行列ができる「たません」のおせんべいが買えました。
明治村で これを食べるのが好きです。

2012/11/25
大人のための文章教室 (1687)
二カ月に一度の 作文教室。
原稿を書き、8人分のコピーをつくって持っていくことになっている。
家から会場まで40分かかるので すこし早めに出る。
会場の近くにはイチョウ並木が色づいて、青空に黄色が映えてとってもきれいでした。

先生から「今日の司会をしてください」と言われた。
どなたの原稿も、その人なりの個性が出ていて、おもしろい。
自分の原稿を読むときは、いつもドキドキする。
わたしにはこの緊張感をもつ時間が大切なのだろう・・。
終了後、先生を囲んでランチを楽しんだ。

2012/11/23
藤工芸 (1686)

藤工芸 おけいこ日。
6人そろって クリスマスのツリー(高さ50㎝)を編む。
材料は皮藤でほとんどを編み、ベルと花びらが丸芯を使用。
全体はシックで落ち着いた雰囲気。
材料選びは、先生が「主婦だからできるだけリーズナブルに」と言われ、セットものは使わず、ひとつづつ揃えていただける。
赤いリボンがクリスマスらしく華やかさを添えていた。

11月も末になったので、
すぐにわが家の室礼のひとつになった。

2012/11/21
『100歳までボケない・・ 』 (1685)
白澤卓二・著 文芸新書
『 100歳までボケない 101の方法 実践編 』
~長寿者9人のアンチエイジング~
最近本屋に行くと、白澤卓二・著の本が目につく。
同じ年齢でも、若く見える人と そうでない人がいるのは、老化のスピードが違うから、というのは よく理解できる。
では本書のように101の方法を実践すれば、いつまでも脳が老いない。
長寿の秘訣に登場する9人の著名人。
「ときめき脳と 断食の効用」のインタヴューを受けておられる瀬戸内寂聴さん(90歳)。
一番若々しく脳も活動的で、真似をしたくなる。
新しいことにも次々と挑戦されていて、読んでいるとわたしまで元気になる。
お寺で生活していても「わたしは破戒坊主」だから、菜食だけでなく 何でも食べられるという。
そして「生きること」は「ときめくこと」と言っておられた。
著者の先生も、
100歳までボケないのは「集中できること」「興奮できること」を生涯にわたって持つこと、
だ そうです。
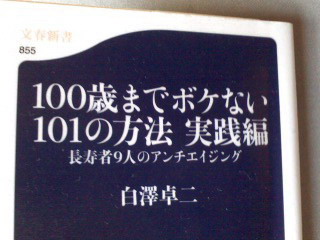
【写真・部分】 白澤卓二・著 文芸新書855
『 100歳までボケない 101の方法 実践編 』
~長寿者9人のアンチエイジング~
2012.4.20.第1刷発行 文芸春秋・刊 @750e
2012/11/17
ドームやきものワールド (1684)

ことしも2012年の「ドームやきものワールド」に行ってきた。
毎年のことでお目当てのお店があり、そこを訪れるのが楽しみ。
香川県「恵子のたのしい家goods」、佐賀県波佐見焼の「藍彩窯」、信楽焼「文五郎窯」「信楽ギャラリー草土」・・などなど。
きょうは小田原市の「薗部産業」さんでお椀と、インドネシアの家具が多くあった店で木の花台を買う。
波佐見焼で陶板を3枚買って、あとはぐっーと我慢。

恒例のテーブルコーデイネートコンテストは見慣れてきたせいもあるのか、あまり感動するもの、「わぁ~いいなあ」と思うものが無くて・・。
匠の職人展のコーナーは宮崎県の梅里竹芸 竹の家具は、繊細で 見ているだけでため息が。
どれも欲しいものだが、わが家に持ってきても可哀想だし、またお値段も手が出ない。
日本の伝統工芸に、匠の職人技に 毎年驚いては帰る・・。



