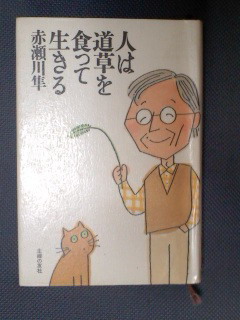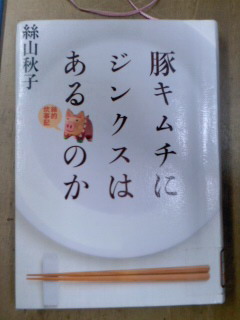2011/07/31
『 人は道草を食って生きる 』 (1323)
『 人は道草を食って生きる 』
赤瀬川 隼(しゅん)・著 主婦の友社・刊
1980年ごろだから、いまから30年ほど前 著者が、外国語教育と国際交流のための民間団体に、勤めておられた。
そのころ名古屋の丸善ビルの事務所で、何度かお目にかかったことがある。
のちに直木賞を受賞され、作家になられた・・。
あの頃は、大作家になられることなど知る由もなかったから、驚いた。
本書のエッセイを読んでいると、あの頃のことも書かれているので、あれこれ思い出され なつかしかった。
「貧乏という名の贈り物~娘への手紙~」という文章では、わたしはお嬢さんも知っているので興味深く読んだ。
優しい著者だが 当時は父として厳しい経済的状況の中で育てられていたのか、と知りました。
お嬢さんも しっかりしていて、小さな子どもたちからもとても信頼される”お姉さん”でした。
今は、著者も 娘さんも お元気で お過ごしでしょうね・・。
2011/07/30
お寿司ランチ (1322)

友人三人が 展示会を見に来てくれるというので、
「カフェギャラリー茶楽」に行く。
この街のことはよくわからないけれど、ここで ランチ。
おいしいところを店主夫人に聞く・・。
彼女は食通らしく、いろいろと教えてくださった。
その中のひとつ、
「お寿司ランチ」は盛り付けもきれいで、刺し身がおいしかった。

「茶楽」でわたしの次に展示会をされる方に 偶然お会いした。
その女性 いわく。「次回の展示会の予約をしたら、2014年7月でした。このギャラリーは人気ですネ」。
わたしは3年先なんて とても予約できない。
そのころは足、腰 立たないかも 知れません・・。

2011/07/29
藤工芸 (1321)
先月 編んだ小さいカゴ。(たて14cm、よこ30cm)
きょう カゴの手を付けた。
茶色に染めた丸芯と平芯で編んだもの。
孫たちが、「ゆかたを着たとき、いいよねェ」と好評でした。

2011/07/28
絵付け (1320)
男性用のマグカップの、素焼きができた。
無地では・・??と思い、
すこし色気が出したくて、
ほんの少し 紅柄(ベンガラ)で、絵を描いてみた。

2011/07/27
みそ汁マシーン (1319)
今朝の日経新聞に掲載されていた(2011.7.26.)。
・・みそ製造大手のマルコメは、
今秋 オフィス向けの小型みそ汁マシンを発売する。
レバーを押すと みそ汁一杯分の液状みそが出てくる。
お湯を注げば すぐに味わえる、という。
コストは具材込みで一杯20円以下の見込み。
コーヒーサーバーもあるのだから、似たようなものか。
それにしても グッドアイデア。
お弁当持参の人が多くなったという。
寒いときなど、あたたかいみそ汁は 心なごみますよね。
可愛い「マイお椀」も用意して、ランチタイムも楽しくね。

2011/07/26
『豚キムチにジンクスはあるのか』 (1318)
『 豚キムチにジンクスはあるのか 』
~ 絲的炊事記 ~
絲山 秋子・著 マガジンハウス・刊
著者は 有名な芥川賞作家。
これほどの賞をとる作家が、こんなにおもしろい、あたかも漫談を読んでいるような本を書かれていたのですネ。
本人が考えて作った料理に関するエッセイ。
餅とパスタの食材を使った料理・・:
白い餅と パスタを、イカスミソースに投入して「コールタール」とか、「ヘドロ」状態に仕上がるというもの。
名前は「チカラパスタ 闇夜風」。
本人は とても香ばしいと書いています。
これは 近いうちに、ぜひ作って食べたい。
ほかに ・・これはいくらなんでも食べたくない、というレシピもありました。
小説家として新しい作品を産むかたわらで、こんな楽しい料理を考えて、新しい料理に挑戦されて お見事ですね。
【写真】 絲山 秋子・著『 豚キムチにジンクスはあるのか 』
~ 絲的炊事記 ~ 絲山 秋子・著 マガジンハウス・刊
2007.12.6. 第1刷発行。 @1200e
2011/07/25
ゴーヤ (1317)
ことしはゴーヤの生育がよくない。
まだ4本くらいしか採れてない。
葉に隠れていたのを採ったら、こんなに大きかった。
(280gもあった)
細いつるに よくも ぶらさがっていたものだ。
身はゴツゴツとして光をたくさん吸収して、
いかにも栄養がありそう。
おひたしにして、ごま油としょうゆで、
おいしく 食べました。

2011/07/24
木曽川学セミナー (1316)
木曽川学セミナー 第7回
「東シベリアのタイガ(北方針葉樹林帯)について」
講師は 岐阜県立森林文化アカデミー 柳沢 直 先生
はじめに温暖化の話。
その中で「永久凍土」という言葉を使われた。
シベリアの 冬季には月平均温度がマイナス40℃にもなるところでは、2年以上も土の温度が上がらず、凍りついている。
その状態を 永久凍土と呼ぶ。
わたしは知らなかった。
シベリアでは 主な樹木が、カラマツ、アカマツ、シラカバの3種類しかない。
降水量は だいたい愛知県で降る雨量の10分の一。
緑豊かなカラマツ林ができるわけがわかった。
種から芽を出し、やがて林になる木は、水不足から根が深くなって、永久凍土の水を吸い取って大きくなる。
なるほど。 改めて 自然の大きさに 感動。
このセミナーは わたしの関心事以外の分野です。
それでも 講師の先生の指導により、わたしなりの小さな発見を 毎回もらって帰れる。
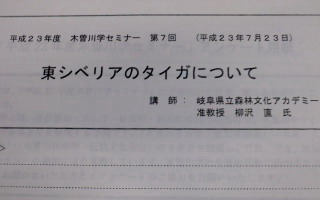
2011/07/23
友と語る (展示会) (1315)
今、わたしの器の展示会を 隣り町のカフェギャラリーで開催中。
友人が来てくれるというので、一緒に行く。
さらに ほかの知人も訪ねてくださったので、
一緒に コーヒータイム。
たまたま趣味や 好きなことの話しで盛り上がり、
初対面の友も すっかり愉しい雰囲気に溶け込んでいた。
良い友に恵まれ、心うきうきの一日でした。

2011/07/22
買い物かご 完成 (1314)

藤工芸の おけいこ日。
先月編んでいた 買い物かごの取っ手を付けました。
取っ手も、いろいろな編み方や、材料(皮籐か、丸芯か、それとも平芯)でも、好みによって選べるので 迷う。
わたしは 一番シンプルに、同じ太さの丸芯で 巻きました。
おけいこが終わったあと、わたしの展示会に行って下さるというので 案内しました。