2008/07/06
夢は大きいのがよい
小学生(3年生)の孫が遊びに来た。
「わたし、子どものフラダンスの教室(10回コース)に通っているよ」と。
大人教室で母親がやっているのを見てやりたくなったので参加した。
この孫は何にでも興味を持ち積極的である。
近い将来の夢は生徒会の会長になることという。
母親手作りのスカートをひらひらさせ、
フラダンスを踊っている姿は可愛らしい。

2008/07/05
着物は合理的だ
今は亡き母の形見となった着物がある。
何枚かは洋服にリフォームした。
羽織りをほどいていてびっくりした。
羽織りも一反で作るときは、丈に合わせて重ねたり折り曲げて、裏地を使わず表地で合わせてある!
要するに切り刻んでないので、ほどけば延ばせて、元の幅、元の長さに近くなる。
リフォームが しやすいのだ。
母は経済的にゆとりがあったのか、大島紬も多く残っていた。
大切にしよう・・。

【写真上】ほどく前の羽織り

【写真下】ほどいていくと裁ち切らず織り込まれていた。
2008/07/04
今夜はカレー
今夜はカレー。
わたしはカレーやおでん、煮込みスープ、豆類を煮るときは、朝 用意する。
一日中スロークッカーで煮込むから、おいしさはこのナベのおかげ。
このナベは、アメリカでホームステイしてきた友人が、あちらではすごく流行していると教えてくれた。
日本で出回り始めて30年くらい。 わたしは3台目。
カレーは普通に市販のカレールーを使う。
そこにわが家流の隠し味を入れるだけ。 余ったら残りは冷凍して、孫の好きなカレーうどんを作ったりする。
この市販のカレールーはアメリカや韓国には無い。
アメリカからきたホームステイの子から「クリスマスプレゼントに送って」と言われたこともある。
韓国の友人たちも大好きで、わたしは訪韓の時にはいつもおみやげに持って行く(激辛用)。
いつか韓国のロッテデパートで、日本のメーカーのカレールーを売っているのを見かけた。 もちろん輸入品になるから、こちらの3倍の値段でした。

2008/07/03
外国人のお客も大歓迎・・・コシノジュンコさん(Ⅱ)
コシノジュンコさんのインタビュー記事の中で、もうひとつ共感するところがあった。
世界のファッションデザイナーとして海外でも活躍されているので当然だが、外国人もよく招かれるようだ。
「外国人より、目の肥えた日本人を迎える時が緊張する」と言われていた。
何年か前までの20年間ぐらい、わが家はホームステイ受け容れをよくしていた。
友人たちから「日本人でも泊めるのは大変なのに、よく外国人を泊めたりするわね」と言われた。
そんな折に「わたしは外国人の方が気が楽よ」と応えていた。
コシノ家とわが家では比較にならないが、気持ちの上では共通することですね。

【写真】当時わが家や近隣の町にステイしていた外国からの人を招いてバーベキューパーティしたときのスナップ写真(1986年)。
2008/07/02
取り戻せ「もてなしの心」・・・コシノジュンコさんからの呼びかけ
日本経済新聞に ファッションデザイナー:コシノジュンコさんのインタビューが掲載されていた。(2008.6.30.日本経済新聞5面)
「日本に伝わるもてなしの心とはどんなものですか」という問いに応えて、
「わざわざ、いちいちということだと思います」という答え。
わたしは「うーん」とうなってしまった。
あまりにも 適したことばに・・・。
お客さまをもてなすために、「ひと手間」を面倒と思わず、そこに心を込めるのが日本人だったはず。
今は、合理的になり過ぎたし、面倒なことは避けたいと省略してしまう。
いつか「家庭画報」という雑誌に「コシノ御夫妻で、お客さまを招く」記事が載っていた。それを見て、センスというか、その美意識に見とれたことを思い出す。
一流と呼ばれる人は、あらゆるところに心配りのできる、敏感な人なのだ、と納得した。

【写真】2008.6.30.日本経済新聞5面オピニオンのページ。
2008/07/01
夏の昼ごはん ・・・・・ 冷そうめん

きょうから七月。
冷索麺(ひやそうめん)が おいしい季節。
わたしは手延べ索麺がよい。
最近出回っているものは 機械延べものがほとんど。
子どものころは、索麺が苦手で 嫌いだったが、
最近はお昼ごはんに よくいただく。
紫蘇の薬味と、生姜、ネギを揃える。
つけ汁を入れる「めんちょこ」は、磁器、陶器、漆器、ガラスと、いろいろ集め、昼ごはんのつかの間、ゆとりを愉しんでいる。

2008/06/30
「40年の道 ありがとう展」・・・書・絵・詩作家 加藤としえさん

きのう木曽川学のセミナー受講を終えたとき、同じ建物の各務原中央図書館三階ギャラリーで、「加藤としえ 40年の道 ありがとう展」が開催されていた。
相変わらず、一目見て加藤としえさんの作品とわかる。
個性的で 光っている作品の数々・・が並ぶ。
もう20年も前、わたしはこの加藤としえ先生に週一回、絵手紙を教えてもらっていた。
会場受付に先生をお見かけしたが、先客とお話をされていたので、話しかけるのを遠慮した。
わたしの家にも あのころの作品や本も大切にしてあります。

2008/06/29
「飛騨川流域をつくる岩石」・・・・・第4回木曽川学セミナー
平成20年度木曽川学セミナー:
第4回「飛騨川流域をつくる岩石」 講師は岐阜大学教授の小井戸由光先生。

わたしは岩石など興味がまったく無いので、今日はいやだなあと思いつつ出席。
岐阜県南東端恵那山付近から富山県境付近まで広大な面積が「濃飛流紋岩」に覆われているそうな。
作られた時代は6500万年前までの中生代の白亜紀後期とか。
地球上からあの恐竜が突如絶滅した時期と一致するという。
当時、地球ではなにが起きていたのか・・。
「濃飛流紋岩」が火山のマグマ・溶岩だまりから作られる様子が、恐竜を絶滅させた犯人像を求める状況調べになると。
わたしでもわかりやすく、理解できるように話をしてくださる。
”動くこと山の如し”が活断層だ、とも。
おかげで退屈しなかった。
小井戸先生は「自分の墓石は岩石(濃飛流紋岩)で作りたい。
でもこの岩石は長方形のものには絶対切り出しできない。
わたしはあまのじゃくだから・・」と言われながら、
本当は岩のごとく硬い人なのだろう。
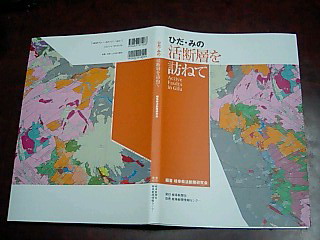
【写真上】「中部地方の立体地形の鳥瞰図」(原図は佐藤正明氏提供)p10page
【写真下】『ひだ・みの活断層を訪ねて』の表紙カバー。 谷、川、耕作地、鉄道、道路、市街地が、ほぼ活断層に沿って並んでいる・・。
※写真はいずれも下記の本より撮影した。
岐阜県活断層研究会 編・著『ひだ・みの活断層を訪ねて』
2008.2.11.刊。岐阜新聞社発行 ¥1800E
書籍販売は岐阜新聞情報センター出版室Tel 058-264-1620
2008/06/28
ANAグループ機内誌『翼の王国』
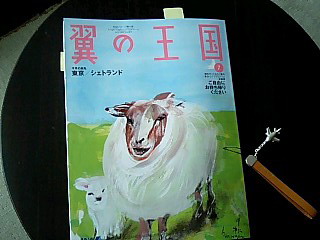
ANAグループ機内誌『翼の王国』2008.7月号に わたしの投稿エッセイが採用された。
半年も前に出かけた沖縄旅行のことを書いた。
この雑誌はフリーマガジンだが 内容は質が高い。
いつも飛行機に乗ったら楽しみにしている。
この号も連載「中国万事通」第16回:「景徳鎮・陶瓷(taoci)」という記事は、陶芸の好きな私にとって 読み応えがあった。
採用のお礼として純銀と本皮製のANAオリジナルストラップが届いた。
大きな飛行機もこんなに可愛らしく、お気に入り。
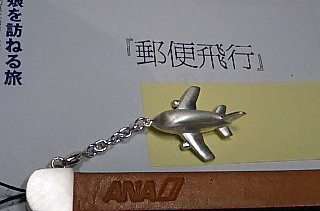
【写真上】ANAグループ機内誌『翼の王国』2008.7月号。
【写真下】お手紙募集「郵便飛行」のページ(部分)と ANAオリジナルストラップ。
2008/06/27
陶芸教室
月1回の陶芸教室の日が近づくと、今度は何を作ってもらおうかなあ、と考える。
今回は型を使って四角皿を作ることにした。
型は「ポリスチレンフォーム」を切って 型を作る。
型の材料をホームセンターに買いに行ったら、畳一枚の大きさのものしか売っていなかった。 「ポリスチレンフォーム」は建築材料なら断熱材として使うもの。
そうだ! 先日パソコンを買い換えたときのダンボール函に緩衝材で付いていたと思い出した。
カッターナイフで切り取り、型ができた。
厚さ5㍉のタタラで、簡単に皿が出来上がり!

【写真】型と これから素焼きに出す皿


