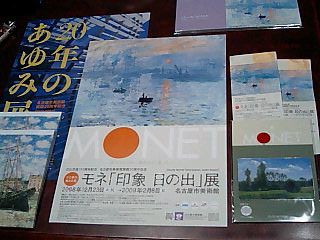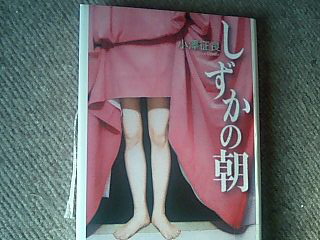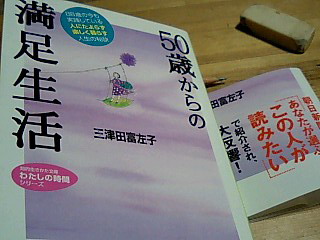2009/01/22
帽 子
冬物バーゲンが始まった。
大型スーパーへ買い物に行き、
「セール」に 引き込まれ、雑貨屋へ。
最近 白髪がふえたので 時々帽子を愛用している。
こげ茶色のアンゴラ帽子が眼に留まった。
4割引だったので 衝動買い・・。

2009/01/21
かぶら。 今が一番おいしい
「雀が宝探しを始めたら蕪(かぶら)蒸しを 作れ」という諺がある。
雀が食べるものに困って、落ち葉の下をつつくほど寒くなったら、
蕪が旬を迎える、という意味。
蕪は 古く奈良時代から 栽培されている。
・・ということで、今時分、蕪を食べなければ と、
蕪料理をする。
わたしは 漬け物(生で食べる)が好き。
友は 鍋物にも入れるという。

2009/01/20
50年ぶりの再会
小学校卒業以来 一度もお会いしたことがない友人。
何年か前にちょっとしたきっかけで、
年賀状のやりとりが始まり、
「会いたいネ」ということで、きょう実現した。
待ち合わせの場所に行っても、
果たしてわかるかなあと ドキドキだった。
何のことはない。 面影があり、
50年の空白は一瞬のうちに消え去った。
なつかしい話しやら、現在の家族の様子の話しで、
3時間あまり、 おしゃべりは尽きることはなかった。
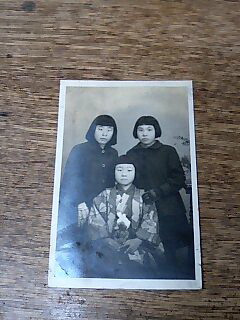
2009/01/19
つみ菜
春野菜の、つみ菜。
毎年3~4月ごろ 浅みどりの葉を摘んでは食べる。
辛し和え、ゴマ和えにしても おいしい。
わが家は みんな好きなので、家庭菜園で育てている。
冬深し 寒の内という今頃なのに、
畑のつみ菜は、もう 菜の花のように 黄色の花が咲いてました。
今の時季に花が咲いたのは、
種から蒔いたのではなく、ポット苗を植えたからかなあ・・。

2009/01/18
『 しずかの朝 』小澤征良・著
以前、この著者・小澤征良のエッセイ『おわらない夏』集英社刊を読んだとき、スケールの大きな人だと感じていた。
この本『 しずかの朝 』は、25歳 独身女性の心の動きを描いたもの。
途中から登場してくる、クーニャという老婦人が、ひょっとしたら入江麻木さんではないかと思いながら読んでいた。
やっぱり最後に「この小説を祖母入江麻木に贈ります」と書いてあった。
上品な言葉の文章が 印象的な本。
それにしても、小澤家は父・指揮者、息子はタレント、娘は小説家・・。
輝かしい才能一家であることよ。
【写真】小澤征良(おざわせいら)・著『 しずかの朝 』
2008.11.30.発行 新潮社・刊 @1400E
2009/01/17
陶芸教室 新年会

陶芸教室の新年会でした。
幹事をすることになった・・。
会場は 時々ランチに利用する和食のお店に決めたので、
出席者に気に入ってもらえるか、心配でした。
ここの陶芸教室に お世話になり5年。
ずーッと前には、新年会をやっていたそうですが、
ここ5年ではやっていなそう。
20人以上の多くの人に来ていただき、
よい雰囲気でした・・。

2009/01/16
ひな人形作り


若い30代の主婦6人と、ひな人形作りをした。
同じ型紙を使って、作ったけれど、
それぞれが個性的にできあがり。
シンプルなので簡単かと思ったが、
バランスをとるのがむつかしかった、と評。
今、陶磁器メーカーでは、
ひな人形の出荷がピークを迎えているそうだ。
最近は、細面の美人顔より、 柔らかい丸顔が人気だとか。
本日の作品は 流行の「和める顔の人形」でした。


2009/01/15
誕生日 1月14日
1月14日 誕生日、2番目の孫が15歳。
中学3年生、高校受験勉強 真っただ中。
生まれてきたとき、看護師さんから、
「きれいな娘(こ)よ」と 言われたのを覚えています。
わたしの作るミートソースが 大好き。
たいしたケガや病気もせずに、
すくすくと育ち、感謝です。

2009/01/14
「50歳からの満足生活」
三津田富左子・著『 50歳からの満足生活 』
知的生きかた文庫 三笠書房
名古屋 広小路のW書店に、この本が何十冊と置いてあり、目に付いた。
「人にたよらず楽しく暮らす」を実践している人・・と、表紙カバーに書き込まれている。
著者のお歳は、大正元年生まれの現在96歳。
この年代の女性が、気ままに、好きなように生きる、
自分の意志を通して生きるというのは、大変なことだったろう。
そういう点では 脱帽!
歳を重ねて 何にもする気力のない人、
退屈な人には ぜひ読んでほしい一冊。
【写真】三津田富左子・著『50歳からの満足生活』知的生きかた文庫 2008.10.10.第1刷発行・文庫本化 三笠書房・刊 @571E
2009/01/13
モネ「印象 日の出」展

名古屋市美術館で モネ「印象 日の出」展 に行って来た。
昨年の暮れから前売り券は 買ってあった。
美術館に着いたらチケット(当日券)を買う人たちがズラーッと並んでいた。(寒い外で)
中に入って さらに驚く。スゴーィ人、人で画が見れないほど!
クロード モネは 150年くらい前に、日本の文化(浮世絵)から強い影響を受けた画家。遠近法、ぼかし、ゆらぎ・・。
日本人の私たちには、だから好かれるのかもしれない。
しっかりと見てきました、モネ「印象 日の出」は。
(・・「印象 日の出」は:“印象派”の名付け元。)