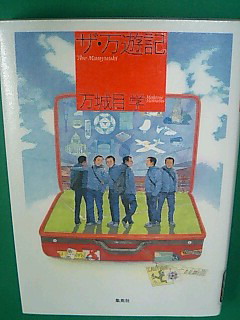2010/07/16
藤工芸のおけいこ
お休みの人がいて、生徒はふたりだけ。
花器を編む。
藤つるで 下の型を編んでおく。
その上を 皮藤で ひし型に編むのだが、
これが むつかしく 苦労した。
先生から「前頭葉が活発に動いてますネ」と・・。
集中力も ここまで。
あとは、次回で 完成させましょう。

【写真】作りかけの 作品。あとは 次回で 完成させましょう・・。
2010/07/15
~介護笑説~『 山姥は、夜走る 』
湯川博士(ゆかわひろし)著~介護笑説~『 山姥は、夜走る 』 朝日文庫
雑誌「クロワッサン」に紹介されていた。
著者は文筆業のかたわら、趣味で落語の出前公演もされている。
還暦過ぎた息子(著者)が、90歳の母を介護する記録である。
介護は精神的にも肉体的にもしんどいものだが、著者は笑いと工夫で乗り切っておられる。
わたしは3年ほど前まで経験してきたのでよくわかる。
著者は上手に肩の力を抜きながら、客観的に観ておられる。
わたしは介護がもう終わったので、気楽に読めた。
老人の話し相手が うまくできれば、介護の半分はできたと言ってもよい。
普通の人たちは、身内だと思うので遠慮のない言葉が出てしまう。
著者は話術がうまく(笑い)、落語が介護にも役立っているようだ。
読み始めて止められないので、電車の中でも 読んでいて、笑いをこらえるのに苦労した。
本来は暗い話しだが、それほどに おもしろい。
介護中の方、ぜひ一読を おすすめする。
ラクになるヒントが いっぱい。
【写真】湯川博士著 ~介護笑説~『 山姥は、夜走る 』 朝日文庫 2010.4.30.第1刷発行。朝日新聞出版・刊 @580e
2010/07/14
オモニの味を食べに
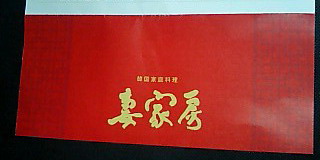
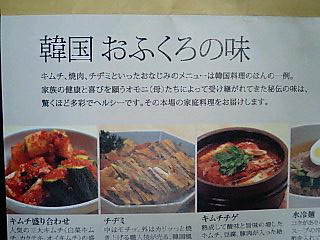
学生時代の友人に会いに 名古屋へ出かけた。
ランチは、前回から約束してあった、韓国家庭料理「妻家房」saikabo。
わたしの韓国の友人も、料理が上手で、チャプチェ、ケムダン、ビビンバ、あわびのおかゆなど、訪韓の折りには いつも食べさせてもらう。
ここでも、そんな家庭料理を食べてみたかった。
「妻家房」では、石焼きビビンバのランチをいただいた。
ごはんはアツアツで お焦げができていた。
具を混ぜると お焦げも混ざって香ばしく、おいしかった。
この店は東京に本店と支店が多くある。
オモニの味もよいが、一度は宮廷料理も食べて、ドラマ:チャングムのような気分も味わってみたい。

2010/07/13
水ようかん作り
暑くなってきたので、水ようかんを作ってみたくなった。
寒天パウダー4gを、400ccの水で煮て、溶かしていく。
寒天液の中に、買い置きの抹茶あん(500g)を少しづつ混ぜながら、煮ていく。
荒熱が取れたら、流し缶かプリン型に入れて 固める。
上品な甘さの“水ようかん”の出来上がり。
甘味の好きな孫や家人は「抹茶の風味があって おいしい」「さすが富澤商店のオリジナルあん だね」との評。

2010/07/12
H22 木曽川学 第5回セミナー
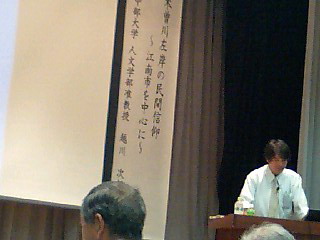
木曽川学セミナー。3回目、4回目と都合が悪く、飛んだので、
一ヵ月ぶりに出席した。
「木曽川左岸の民間信仰~江南市を中心に~」
講師は中部大学の 越川次郎先生。
木曽川中流域左岸の江南市に在る、民間信仰に関する調査報告のような内容。
家からも近くて、馴染みの地名が出てきて、いくつかの神社には行ったことがあったり、知っているところなので、興味深く聞かせていただいた。
民俗学を研究されている・・と、何か年輩の人を連想するが、まだ30代の若い講師で、プロジェクターなどIT機器を使って写真も多く、華やかさはないが なんとなく落ち着いた ぬくもりのひとときでした。

【写真】御嶽山大権現。ムラの神様として祀られている。
2010/07/11
おたまじゃくし
外孫(小学2年)が遊びに来て、
田んぼでおたまじゃくしをとってきた。
わたしは 女の子どもしか育てたことがないので、
田んぼの生き物・・魚、水生昆虫、カエルといったものに、
ほとんど無縁で過ごしてきた。
おたまじゃくしも、何十年ぶりかで身近かに見た気がする。
この孫はまた、特に生き物が好きみたいで、
わが家に来ると、田んぼとか里山に行きたがる。
性根は優しい子で、おたまじゃくしで2~3時間わが家で遊んだら、自分で田んぼに戻しに行ってきた。

2010/07/10
『 ザ・万遊記 』万城目 学・著
万城目 学(マキメ マナブ)・著 『 ザ・万遊記 』 集英社・刊
著者の存在は、エッセイ集『ザ・万歩計』を読み、知った。
今回もエッセイ、読み応えがあった。
中でも日曜日のテレビ番組「渡辺篤史の建もの探訪」の大ファンだという。わたしも時どき観るので、著者の感想は どれもよく解かる(この本では、毎月、今月の渡辺篤史として登場する)。
この番組では、実際に在るお宅を訪問し、男優である篤史さんが紹介するというもの。
わたしも すてきな建物ばかりで、うらやましく観ている。
著者が言うには、篤史の視点・言葉が添えられているからこそ、画面の中の世界が一気に彩りを得るのだ、と。
何のことはない、テレビで放映された家を見たら(著者は実際に見に行かれた!)、いたって“普通の”家だったそうだ。
真新しいもの、飛びぬけて素晴らしいものは、そうそう簡単には見つからない、と著者の感想。
それを、観ている者に、素晴らしいと感じさせる渡辺篤史は、すごい人だと言われる。
なるほど 気が付かなかった。
2010/07/09
陶と藤のコラボ (2作品)
わたしらしい作品だと思うのは、
陶の作品に 藤をあしらったもの。
ずーっと長年 作り続けている。
今回、皿というか、菓子器にするか、二枚できた。
写真のように皮藤の細いものを巻き付けた。
大きい方は水色なので、藤を水色に染めてから巻く予定。

2010/07/08
失 敗 ( 創作花器 )
本焼きが 出る日。
楽しみにしていた 花器そのものは、思うように出来た。
が、流木を入れるようにしていた個所のうち、
一つが 薄すぎて 割れてしまった。
厚みの計算間違いで、
もう少し奥へ 木の枝を入れたかったのになあ。
・・・ 再度 挑戦しようか。

2010/07/07
蕎麦猪口を作陶
蕎麦打ちを習っている人から「欲しいので、作って」と頼まれた。
猪口は お蕎麦の道具として使うが、今は 湯呑みと兼用でもよいような型が流行っているそうだ。
蕎麦猪口は江戸時代に、江戸で栄えた“そば文化”の名残りで、猪口は骨董も多く出まわり、好きな人には 魅力のある器の一つ。
とりあえず 10個 ロクロで 型を挽いた。
絵付けや 色は 任されているので、これから考える。