2015/08/25
中島京子・著 『 長いお別れ 』 (2024)
*
中島京子・著 『 長いお別れ 』 文藝春秋・刊
新聞の書評が良かったので 読んでみる。
二人住まいの老夫婦の夫に認知症が始まる。
少しづつ記憶を失くしていくから
「長いお別れ」と言うのだ。
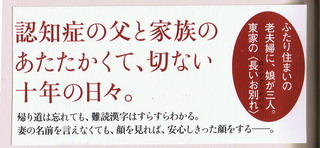
本書の中の東昇平さんと奥さんは、
夫が言葉も記憶も失われたけど、
長い間の生活から
ふたりにしかわからないコミュニケーションがあったのですね。
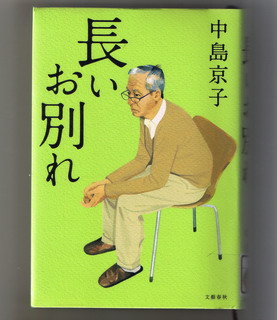
わたしの母が 軽い認知症だった。
わたしは解からないことばかりで、よく 専門の介護の方に
扱い方を教えてもらった。
今なら もっと上手に、
母が居心地良く 生活(くらせ)てあげられたのにと反省する。
【写真上】『 長いお別れ 』の帯封から転載。
【写真下】中島京子・著『 長いお別れ 』文藝春秋・刊
2015.5.30.第1刷発行 @1550e
*
2015/08/20
八月のおけいこ (藤工芸) (2023)
*
陶工芸のおけいこ日。 このクラスは4名。
年齢差は15歳ほどの開きがある。
手がける作品もいろいろ。
かご、人形、花・・とバラバラに好きなものを作っている。
おしゃべりとなると、政治のことや おしゃれ、孫のこと。
料理、レシピ・・まで何でも話題になる。

きょうは7月に大相撲名古屋場所を観てきた人がいて、
そのときの話題で盛り上がった。
ティタイムは お土産の「すもうくっきー」をいただいた。

わたしは きょう女の子が出来上がった。
次回は男の子も作り、ペアにしよう・・

*
2015/08/15
終戦記念日 特別企画展へ (2022)
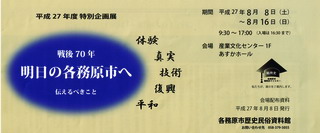
終戦記念日の特別企画展・・ 隣り町で
「戦後70年 明日の各務原市へ 伝えるべきこと」が開催中。
わたしはこの町へおけいこ(藤工芸、作文教室)に通うので
馴染みがあり、見に行ってきた。
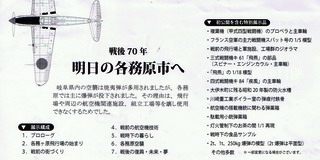
この町はいまから100年前・大正4年の建設工事開始から
飛行場と航空機産業を中心に発展してきた。

藤工芸の先生のお宅が飛行場に近いので、
飛行機の爆音はすざましく、話しはいつも中断する。
複葉機のプロペラと主車輪、フランス空軍の戦闘機・・など
めずらしい実物展示も見られた。
こうした機会に多くの市民が関心を持ち、
さらによい日本国を目指すようになるといいですね。
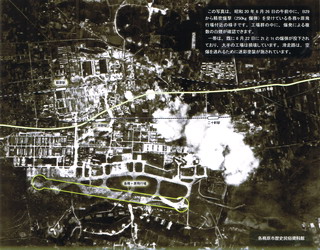
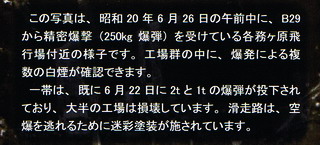
*
2015/08/07
池田勇人さん・・・・政治家・首相 (2021)
*
朝食に もち麦入りのリゾットをよく食べる。
ふと、「貧乏人は麦を食え」と失言したとされる、
有名な首相が居たのを想い出す。

昭和35年、友だち仲間四人で東京へ遊びに行った。
池田勇人首相の令夫人満枝さんが、
友人仲間の母とお友達ということで、
四人を私邸に招待してくださった。
私邸の門の横に真新しい記者団用のトイレが5個も在り、
玄関の脇にポリスボックスが在るのが印象的でした。
夫人は優しい人で、学校の後輩でもあるわたしたちと
学生時代の話で会話がはずんだ。
池田総理は 新聞雑誌ではおおむね 今も評判がよい。
いつか目にしていた新聞の、昭和回想記事と書評から、
総理大臣秘書官・伊藤昌哉さんの著書を知った。

隣りの町立図書館で見つけてきた。
昭和60年発行。さすがに本は黄ばみ焼けている・・
伊藤昌哉・著 朝日文庫
『 池田勇人とその時代 ~生と死のドラマ~ 』
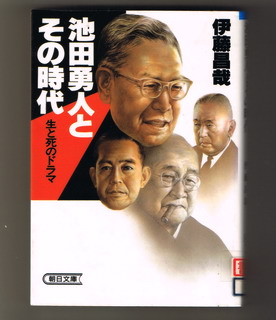
首相になったのは昭和35年(1960)7月。
安保改定のあとの殺伐とした時代ではあったが、
「所得倍増計画」と「忍耐と寛容」の政治を目指した。
自分の青春の時代の社会なのでなつかしさと、
池田総理は偉大な男性だったのだと思いを馳せながら、
一日中読んでいた。
歴代の首相夫人の中で、
記者団に一番評判が良いのは池田首相夫人だ、
と、なにかの新聞記事で読んだことがある。
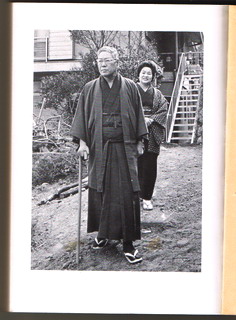
【写真中央】伊藤昌哉・著『池田勇人とその時代』~生と死のドラマ~ 朝日文庫・刊 昭和60年8月20日第1刷発行
【写真下段】上記著作扉写真を撮影。池田勇人首相と満枝夫人
*
2015/08/06
夏まつり (2020)
*

第36回 日本ライン夏まつり
納涼花火大会が木曽川河畔一帯で 8月10日に開かれる。
当日は人出が多いので とても行かれない。
(去年の人出は27万人だそうな)
鵜飼い見物のお客さんサービスを兼ねて。
8月1日から9日まで 木曽川ロングラン花火が
午後8時ごろ 10分間あがる。

ここ数日は熱帯夜つづき。
夕涼みがてら、夏の夜空に舞う華を見に行く。
鵜飼い船と鵜飼いの篝火を橋の上から 眺めたあと、
花火はわずか10分なので すぐに終わってしまった。
それでも充分 夏の夜が楽しめた。
孫とアイスクリームを食べながら 帰ってきた。

動画も撮りました・・・
http://www.satoyama-koubou.jp/ または
https://www.youtube.com/watch?v=8ic4mDHHhjE#t=239
*
2015/08/03
クルマの 検査入院 (2019)
*
わたしのクルマ(cube)を検査修理に出した。
一日あずけることになり、代車で帰る。
新車である(X-TRAIL)。
驚いたことに エンジンのスイッチを押したら
”こんにちわ”という。
どこかの外国人がこれを体験したらびっくりするだろう。
はじめて免許証を取ってから50年になるが
技術の進歩はすご~い。

孫のふたりは この車が大変気に入ったという。
わたしは走ってくれればよくて、
車種もたいしてこだわらない。
現在の愛車も10年ほどになるが運転席から見やすくて
何の不自由も感じてない・・

*
2015/07/31
食事会 (2018)
*

*

*

高校時代の友だちと 半年に一度 食事会をする。
病気で出られなくなった人もいる。
きょうはは 5人で。
女子校で一クラス50人くらい居た。
海外、東京、九州など遠方で暮らしている人も結構居る。
あと何年 元気に出られるかわからないが、
他の人にも声を掛けよう・・と決めた。
猛暑の中 よく出てきて下さった・・

おいしい料理を味わって、大いにおしゃべるをして
愉しく過ごせましたよ。
また次回 期待して!!

*
2015/07/27
『 ほんとうに70代は面白い 』 桐島洋子著 (2017)
*
桐島洋子・著 『 ほんとうに70代は面白い 』海竜社・刊
桐島洋子著『聡明な女は料理がうまい』を読んで以来、
久々に読んだ。
雑誌その他で
著者のエッセイや対談などはよく目にしている。
帯に書かれた「聡明な女は素敵に老いる」
・・ 身近な人にも言える言葉だ。
本書では 自宅に「森羅塾」を開き
活躍されている様子も描かれている。
「腸は最大の免疫器官」の節で述べられているように、
およそ病気とは縁の無い「医者いらず」の著者。
70代 健康であれば「面白い」と。
・・わたしも同感。
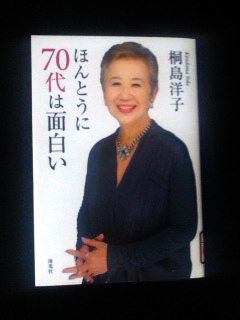
【写真】 桐島洋子・著 『 ほんとうに70代は面白い 』海竜社・刊
2014.12.17.第一刷発行 @1300e
*
2015/07/26
野菜の色 (2016)
*

(上:オクラの花)(下:ゴーヤの花)

今朝、小さな家庭菜園に居る。

(上 ゴーヤ。下 ししとう)

ゴーヤ、きゅうり、ナス、ピーマン、・・が
食べきれないほど採れる。

(わが家のミニトマトは3種)

完熟した赤色のミニトマトに目がいく。
毎朝 1㎏以上も採れる。
トマトは生食でも、加熱して美味しさアップでも
楽しんで食べている。

*

ナスのところに来た。
皮の紫色はつやつやと輝いている。
ヘタと皮の境い目が紫と白のグラデーションになら、
あまりの美しさに しばし見とれる・・

(上:長ナスのあかちゃん 下:十六ささげの花)

愛知県の特産といわれる十六ささげは
この2~3日 食べごろ。
中の豆が16粒で この名が付いた。
やわらかくて食べやすい。

よく見るとうす緑のさやの先に 紫色がすこしある。
これがなんとも可愛いのだ。

このようなささいなことに気が付き
「すごいなあ」と思える。
・・ 歳を重ねたということでしょうか。

*

*
2015/07/18
『 それでも私が捨てられなかったもの 』 (2015)
*
近ごろ親の亡きあとの家の中の片づけに困ってる、
という人の話しをよく聞く。
自分の両親の時は引っ越しを三度しているので
そのたびに捨ててきた。
母がきれい好きで自分の身辺をよく片付けていたので
ものが少なかった。
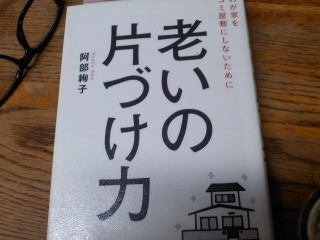
『 老いの片づけ力 』 阿部絢子・著 大和書房・刊
「老いの片づけ力」の著者は
家事研究家の第一人者として名を成しておられる。
そのお母さんのゴミ屋敷が
たちまちきれいに変化する様子が描かれる。
それでも実際は片づけは大変な労力だ。
身につまされたので、
わたしも元気な時に 少しでもやろうと決心。
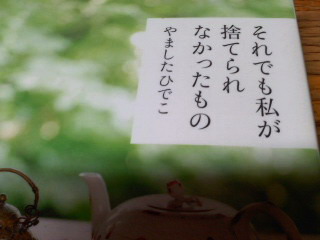
『 それでも私が捨てられなかったもの 』やましたひでこ・著
「それでも私が捨てられなかったもの」の著者は
ヨガの哲学「断行、捨行、離行」から着想を得た、
「断捨離」ということばで片づけの支持を受けた方。
本書には著者の「捨てられない」ではなく
「捨てたくないもの」が 物語りにされている。
・・これは わたしにもいっぱいある。
若い時に手に入れた好みの器類。
メキシコ、トルコ、韓国で求めた陶器類・・
日常、わたしが作った料理をおいしく見せてくれる器類。
やっぱり捨てたくないものは多い。
これから少し考えを改めて片づけなくては・・と気付いた。
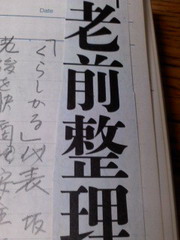
【写真上】 阿部絢子・著『 老いの片づけ力 』
大和書房・刊 2015.1.23.発行 @1400e
【写真中】 やましたひでこ・著 イーストブレス・刊
『 それでも私が捨てられなかったもの 』
2014.9.7.刊 @1500e
*


