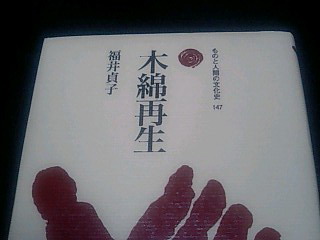2009/11/18
『 名作の書き出し・・漱石から春樹まで・・』
『 名作の書き出し ・・漱石から春樹まで・・』
石原千秋・著 光文社新書
本書では 作家15名の代表的な小説を、どう読んでいったら おもしろく読めるか、が書かれている。
わたしは その中で漱石の『それから』が気になった。
高校生の頃 読んだと思うが、主人公の「三千代」という女性の名前は覚えていた。
今までにどれだけの本を読んだかわからない。
本書によると「自分だけの物語」だと思っているが、実は、そのほかにも物語がこっそり隠されていて、それを見つけ、読み解くのがおもしろいという。
なるほど、この『それから』も、代助と三千代の恋の物語でありながら、実は遺産相続にかかわるテーマ(家庭崩壊する物語)が書かれているということ。
さすが著者は 深い読みをされる、と感心した。
【写真】『名作の書き出し・・漱石から春樹まで・・』 石原千秋・著 光文社新書 光文社・発行。 2009.9.17.発売。@861
2009/11/17
わたしだけの 首飾り
昨日のクラフト展(そうだがや)。
アクセサリー用の 毛糸を買った。
毛糸屋さんが「この2種類の糸を 鎖で編むだけでよい」と言われた。
ステンドグラスの作品のところで、
キノコの型のペンダントヘッドを売っていた。
両方 合わせたら、わたしだけのネックレスが出来上がった。

2009/11/16
第13回「 おもしろそうだがや 」

毎年 いまごろの時期に、クラフトフェア「おもしろそうだがや」が開かれる。主催は「クラフトマンの会“そうだがや”」だが、城下の各町内のまちづくり・発展会が共催参加する。
初めのころは この近くのクラフトマン達の出店がほとんどだった。
最近は 地元よりも 遠くからの出店者が多くて びっくり。
わたしのお気に入りは、岐阜市からの糸屋さん(毛糸・原毛)。
ことしも お買い上げ。
いちばん好きなのは「遊木」と名づけられた お店。
木と漆の手びねりで お盆や器を作ったもの。
先日も テレビで放映されたと聞いた。
作者もわたしと同年代。 笑顔のきれいな女性。
はるばる白馬村からの出店で、それは それは すばらしい作品の数々でした。本日は予算上買えませんでしたが、いつかは欲しいもののひとつです。
年を重ねるごとに 楽しさの増すクラフトフェア・・。

2009/11/15
もみじ寺 継鹿尾山 寂光院

(継鹿尾山寂光院。もみじのトンネル 300段の階段で本堂へ)

そろそろ紅葉してるかなぁ、と買い物の帰りに寄ってみた。
もみじ寺 継鹿尾山 寂光院。
土曜日の午後(朝は 雨が降っていた)。
紅葉はまだ少し早いが、人はいっぱい。
階段300段上がると本堂。 市内の絶景が見られる。
この寺は「尾張のもみじ寺」と言われ、この地方では名高い。
今年は もみじ寺の紅葉 見ました・・。
ところで 今頃の季節、「もみじ狩りに行く」と言いますが、
「狩り」は獣を捕らえる意味で使われていたものが、
草花を眺めたりする意味にも使われることから、
「もみじ狩り」と言われるようになったという説がある・・。

(寂光院本堂展望台。犬山城、名古屋の高層ビルも一望できる)

2009/11/14
若いお母さんたちの 陶芸教室
若いお母さんたちの 陶芸教室。
先月は 台風でお休み。 二ヶ月ぶり。
先回の作品が 出来上がっていた。
ひもで作った角鉢(20㌢正方形)(Mさん作)が人気でした。
今回、手ロクロに挑戦して、茶わん作りをしたいとの希望。
粘土を馴染ませる段階で、徐々に拡がり 形がくずれていってしまった。
茶わんが 鉢の大きさになったが、まあまあ きれいな仕上がりで、教えるほうも ほっとした。
そのほか しゃもじ立て、長方形の皿、角鉢など、
個性豊かに 出来上がり・・!

2009/11/13
柚子こしょう
何年も前に、友人からお土産にいただいた、福岡県柳川市の名産「柚子こしょう」。
それ以来、ずーっとこれを使っている。
藤田みどり・著『北鎌倉のお庭の台所』(主婦の友社)を見ていたら、柚子こしょうの作り方が載っていた。
著者は、マヨネーズに混ぜる、と言われる。
今夜は“おでん”なのに・・・。
でも、マヨネーズに柚子こしょうを混ぜて、大根や里芋に付けて食べたら、洋風になり おいしい・・!
高校生の孫と わたしは 気に入った。
わが家の庭も 今、柚子の実が たくさんぶら下がっている。
作ってみようかなぁ。

(マヨネーズに柚子こしょうを混ぜて・・)

2009/11/12
「禅の心と美」展 (妙心寺)

名古屋市博物館で「妙心寺 禅の心と美」展を見てきました。
禅を通して悟りを開く妙心寺の教えは あまりわかりませんが、信長、秀吉、家康などの武将の篤い信仰心のせいか、わたしの住む中部地方には、妙心寺派の寺が多くあり、日ごろ少しは身近に感じている。
仏像、屏風絵。 名品は見ていると知的な感じがして、すごーぃ世界だなぁと思う。
一番、見て飽きなかったのは「山水楼閣人物図 螺鈿引き戸」。
わたしは螺鈿細工が好きなので、この夜光貝の薄片を貼ってある引き戸に惹かれた。 これは寺の正堂と方丈を仕切る引き戸に使われていたとか。
もうひとつ 「七丈袈裟」。14世紀のものらしい。
袈裟は僧が羽織る長方形のもので、幅が七つに分かれるものが七丈、九つに分かれるものが九丈袈裟と呼ぶらしい。
おそらくこれは夏物で、布地は麻チョマだと思う。 この頃からも チョマは自然素材として活躍していた。
すこし擦り切れたところもあるが 長い間 耐えている。
よく 残っているものだ。
秋雨の中、多くの見る人で にぎわっていた。

2009/11/11
アスパラガス。 赤い実が・・
アスパラガス。 多年生草本植物。
初夏に 次から次へと 芽が出て成長し、よく食べました。
昨日、ふと アスパラガスを見ると、
赤い実がいっぱいついていて、びっくり!
実が生るなんて知りませんでした。
友だちに聞くと、雌雄異株で、秋に実が生るのが雌株で、
雄株は実が生らない、と。
野菜の実も きれいです。

2009/11/10
お地蔵さん

森のマーケットで わたしの作ったお地蔵さんが 人気でした。
朝一番に 中年の男性が見て、「僕も陶芸をやっている」と言って「この地蔵さんはいいねえ」と。
「どうやって作ったの?」と聞かれた。
それから また30~40代くらいの男性にも「これ 分けてくれませんか」と言われた。
夫の友人にも「これ いい顔してる」とほめられていたので、差し上げたら 「玄関に飾って 毎日 ながめてるよ」と言っていただいている。 男性に人気がある。
古くから 人は、願いごとがあると、十のご利益があると伝えられるお地蔵さんに、手を合わせ、祈りをささげてきたそうだ。
わたしは 友人の「こんなの作ってみて」と絵を描いていったことから、自分で工夫して作っている。
みなさんに「可愛いい」と言っていただけるのが励みで、
懲りもせず作陶している。

(わたしのお地蔵さんは、身体と頭を別につくって 合わせる。)

2009/11/09
『 木綿再生 』 -2-
福井貞子・著 『 木綿再生・・ものと人間の文化史 147 ・・』
法政大学出版局・刊
本書を読み出したとき(BLOG 11月7日)、佐々絣(さっさかすり)に出会い、驚きから さらに『木綿再生』を続けて読む愉しみが増えた。
著者が結婚し、並々ならぬ苦労をし、通信教育で教師の資格を取ったこと。また、大姑に絣を織る手ほどきを受けながら、伝統のある木綿を守ってきた、という人生遍歴は、読んでいて感動した。
自分より十年の年の開きのある女性。
重労働、男尊女卑のまだ残る時代、このように家族もろとも衆目にさらされるのは、よほど勇気の要ったことと思う。
日本伝統工芸展、その他 数々の賞に入選されている。
その間には きびしい修行と多くの涙が流されていた。
本書は著者の自伝であり、本書こそ「ものと人間の文化史」にふさわしい一冊。
今また 世の中「絣」に興味を持つ人が多くいる。
わたしも2年ほど前、母の着物から 藍と白の織りに惹かれ、ブラウスを作ってもらった。

(母の着物から作ってもらった ブラウス)
【写真】福井貞子・著 『 木綿再生・・ものと人間の文化史 147 ・・』法政大学出版局・刊。2009.2.18.初版第1刷発行。@2700e