2010/07/26
歌手・石井好子さん 逝去
シャンソン歌手の石井好子さんが 逝去された。
1963年ごろ、高校時代の親友だった I さんが、パリへ絵の勉強に行くので、羽田空港まで見送りに行った。
遠目だったが 石井好子さんを見かけた。
まだそれほど有名ではなかったころなので、石井さんの周囲も 静かな様子。
同じロビーで 料理研究家の江川トミさんも、にこやかに皆さんに挨拶をされているのを拝見した。
1ドル360円のころにフランスへ行けるような人は、まだ ごく わずかだった。
46年も前のことだが、忘れられない。
石井好子さんはあれから、
日本のシャンソン界では なくてはならない歌手となられた。
それに 料理本も出版されるほど 料理も上手で、
いろいろ才能のある女性。
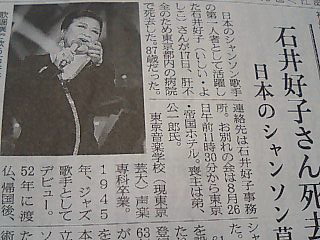
2010/07/25
第6回木曽川学セミナー(松田之利先生)
2010年 第6回 木曽川学セミナー
岐阜女子短期大学長の松田之利先生による中世史、
旗本坪内氏分家の「自立」運動 の講演。
正直言ってわたしは歴史知識に乏しく、苦手な分野。
だが、身近な地のことでもあり、松田先生の話し方が上手なので、また、適当なジョークも交えての話しはおもしろかった。
(幕府直属の)旗本の家にも、庶民とあまり変わらない生活苦もあったのか と苦笑した。
こんな風に解説してもらえば、歴史オンチのわたしも楽しめることを気付かされた。
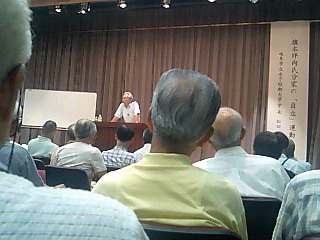
2010/07/24
親子陶芸教室
今年も 親子陶芸教室の指導をしてきました。
昨年に較べて、小さい子どもさんが多かった。
打ち合わせでは、作品はお母さんがひとつ、子どもさんもひとつということだった。
大きい子は自分の作品を ひとつ作り終わると、
つづいてもっと 動物を作ったり、ペンダントヘッドを作りたいとのことで、
「もう 好きなように作らせようか」と、
参加費(材料代)のことは考えないことにしました。
同じ市民なのでボランティア精神で・・・、
粘土にさわる楽しさを味わってもらえば良し。
「ああ 面白かった」という声が聞けた。

2010/07/23
夏 休 み
まだ入学式が終わったばかりと思ってたら、
もう「なつやすみ」。
5人の孫は、高校生ふたり、小学生3名。
み~んな元気で だれも病気で休まずに通学できた。
60年も前の小学生だったわたしは、
病弱で大人になるまで生きられないと、
町医者から言われていたとか。
健康はいいなあ。
40日間 楽しく 元気に過ごしてほしい。
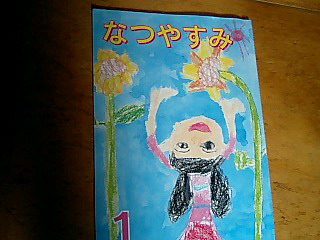
2010/07/22
ティータイム
栗を使った上生菓子で有名な、恵那の川上屋のお菓子をいただいた。
ティータイムは 栗饅頭と緑茶にした。
湯呑みは 先日 クラフト展(岐阜県の朱山窯)で買ったもので、お気に入り。

(恵那:川上屋の栗饅頭)(朱山窯の湯呑み)

2010/07/21
ブラウス と 帽子

古布からの リフォームが 盛んである。
わたしは亡き母の着物が多くあり、
一枚づつ リフォームをしてもらっている。
センスのある人の助言が大切で、
間違えば 台無しになってしまう。
今回は 更紗模様の着物から、
半袖のブラウス と 帽子。
シルクなので 蒸し暑い いまの季節には、
心地よい・・。

2010/07/20
赤染 晶子・著 『 うつつ・うつら 』 文藝春秋・刊
赤染 晶子・著 『 うつつ・うつら 』 文藝春秋・刊
(本書はⅡ部構成の作品集:「初子さん」と「うつつ・うつら」)
赤染晶子さんの「初子さん」を読もうと思ってたら、
7月15日に第143回芥川賞で受賞のニュースに少し驚いた。
(受賞作品は『乙女の密告』:「新潮」6月号)
『うつつ・うつら』の中に、もう一編 収められているのが「初子さん」。
少しおんびりとした 若い女性で、パン屋さんの二階に下宿して、洋裁の仕立てをして生計を立てているのが、主人公の初子さん。
このパン屋の夫妻も、アンパンとクリームパンのみ販売していて、時々 中身を入れ間違うという人間味あふれる人物。
30年前には こんな生き方をしていた人が多くいたのだ。
なつかしかった。
著者はまだ35歳。
「初子さん」に登場するパン屋の娘のモデルかなあと思われる。
でも、この女の子は小学校一年生なのに、学校から家への帰り、いつも迷子になるような素朴な少女。
読んでいて ほっとする時代を感じさせてくれました。
2004年の第99回文学界新人賞受賞の作品。著者は短い間に、こんなに賞に恵まれた天才作家かも・・。
これから 期待してます。
【写真】第143回芥川賞・直木賞受賞者決定を報じる日経新聞2010.7.16.号。 赤染 晶子・著 『 うつつ・うつら 』 文藝春秋・刊。2007.5.10.第1刷発行。@1200e 初出:『初子さん』:「文学界」2004年12月号。『うつつ・うつら』:「文学界」2005年10月号。
2010/07/19
ゴーヤ炒飯
ゴーヤが 毎日採れるので、昼に「ゴーヤ炒飯」を作った。
ブログで読んだ人のレシピによると、
桜エビ、ごま、ゴーヤを炒め、ごはんを加えるとあった。
わたしは ベーコンとピーマン、ゴーヤを入れて作った。
ゴーヤの食感がよく、苦くもなく おいしかった。
また 作ろう。 ワカメスープも一緒に・・。

2010/07/18
木曾川学の遠足


(妻籠宿へ)(妻籠宿本陣:南木曾町博物館)

バス旅行は 上天気。
木曽路の歴史を探る旅で、南木曽町・妻籠宿を訪れた。
以前にも(2年前)、この地は家族で来たことがある。
今回は愛知淑徳大学の谷沢明先生の、やさしい説明付きなので、よく分かった。
(国の重要伝統的建造物群保存地区としての 妻籠宿が)
日本の電力王:福沢桃介ゆかりの「桃介橋」や「柿其水路橋」も、個人旅行ではなかなか行けないところを見ることができ、充実した、楽しい日帰りの旅でした。

(桃介橋:木橋の吊り橋を渡る)(導水路式発電所への水路橋)

2010/07/17
天 災
梅雨明け 間近。
愛知県(と 岐阜県)でも、大雨。
一部地域では、避難勧告が出たところもあった。
うちの孫たちも、学校帰りが 心配された。
隣り町では 車ごと流された方も居たり、トラックが何十台も流されたりと、信じられない災害になった。
いつも よく通る道路なので、なおさら驚き。
水の災害の怖さを、
こんな身近で 感じました。




