2010/12/23
「 おしょくじ処 今 」 (1103)

知らない人のブログを見ていたら、「おしょくじ処 今(こん)」のランチが紹介されていた。
江戸時代末期の建物を移築して・・とあり・・、これは ぜひ行かなくては と。
名古屋市緑区鳴海町(有松)は、伝統ある「有松絞り」の産地。
友人がここまで通って「有松しぼり」を究めている。
この友人に さっそく話して、実現した。
竹林に囲まれた門から 玄関までのアプローチもステキ!!


松花堂弁当(昼席)を予約してあった。
見た目もキレイで楽しみ。
その上単品でカキを焼いたものを追加。
(プリプリのカキ。絶品の味)
味もよく、誘った友人たちも 大喜び。
みんなで「ここ当分は はまるネ」と。
それにしても 少し遠方ですネ(車で一時間半)。


おしょくじ処 今(こん):
名古屋市緑区鳴海町細根16-7
2010/12/22
さつま 揚げ (1102)
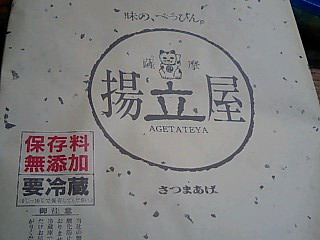
鹿児島出身の方に、さつま揚げをいただいた。
いまは便利で、生モノでも クール便で届けられる。
ごぼうや ニンジン入りは よく食べたが、
チーズ入りや さつまいも入りは、珍しかった。
わが家では、とくに チーズ入りがおいしいと 人気でした。

2010/12/21
ポチ袋(心づけ) (1101)

となり町の大型ホームセンターへ 買い物に行った。
目的のものが見つかってから、ブラ~っと見ていたら目に付いたもの。
お正月が近いからポチ袋かなと思ったら、「こころつつみ」(多当型ぽち袋)と表示してあり、表書きが 目的別に書かれていた。
「 おめでとう 」「 ほんの気持ちです 」「 大変お世話になりました 」
「 ごくろう様 」「お茶でも飲んでいって!」「 感 謝 」「 よい旅を・・」
「 頑張って 」「 気をつけて帰ってね!」・・など。
わたしの時代に人は、これらを白い紙に包んで そーっと渡したものだ。
これは便利でいいかもしれないが、ここまでする必要があるのかしら。
自分で ひと言、言葉を書けば済むことだし、そのほうが心がこもっていると思う。
・・「大きなお世話」だと思うグッズ。
(シャクにさわるがキレイで、 自分も もらったら・・・うれし~い!)

2010/12/20
ブログ 3年 お地蔵さんの ひとりごと (1100)

ブログ 3年 お地蔵さんの ひとりごと・・。
1007年12月18日から3年間、毎日 ブログを書き続けてきた。
初めは こんなはずではなかった。
始めてみると、自分のことでも いろいろな 気が付くことがあり、
飽きもせず、いままで・・・という感じ。
三重県や 松本や つくば の方たちと オフ会したこと。
わたしのブログから、陶器や料理教室の 同じ生徒になった人もいる。
コメントを通して、新しいことを教えてもらったり、教えたりと、
自分の狭い世界が 拡がったような気がする。
・・これからは あまり無理のないように、
「小さな発見」や「驚ろき」に 気が付くような日常を過ごし、
残りの人生を、生き生きと語れるようなブログを目指そう・・。

2010/12/19
LDL(悪玉コレステロール)が高い (1099)
市が主催する「からだ・いきいき講座」に 参加。
一年間で 体重も減り、中性脂肪も正常値になった。
LDL(悪玉コレステロール)だけが、あと少し高いので、
講座に 出席。
管理栄養士の先生から お話しを伺っていると、
わたしの場合は、日常の食事に気を付ける以外にない。
いままでコレステロールを多く含む食品が大好きなものが多く、
(卵、ししゃも、たらこ、ケーキ、シュークリーム・・)
摂り過ぎていたのを 反省しました。
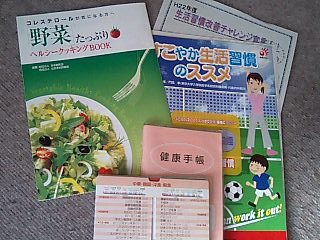
2010/12/18
正月飾り (1098)

ことし最後の藤工芸教室で、
お正月飾りを作った。

丸芯を使って、ウサギを編んだ。
松葉は グリーンに染めた藤で作り、松ぼっくりも添えた。
あとは買い入れた梅の花や竹を添えてまとめたら、
立派なお正月飾りが出来た。
帰宅して、玄関に置いたら、パーっと明るく、
新年を迎える準備のひとつが終わった気分がした。

2010/12/17
「手づくり ごまだれの素 」 (1097)
普茶料理のおけいこの日。
部屋に入るとすぐに、かわいい瓶が積んであるのが目に入った。
先生が「Tさん(わたしの名)、ごまだれの素を 作ったよ!」と。
ついに商品化(?!)
ゴマを摺って、しょうゆと砂糖を加えたものだが、
これが 単純なようで 奥が深い。
先生は、すり鉢でゴマを擦り続けて、肩が痛いとか。
ゴマもよく擦ればよい ということではなくて、
舌ざわりと 微妙なしょうゆの分量など、
長年作り続けた経験が、おいしさの秘訣のよう。
「ギャラリーで販売するようになったが、おかげで すぐに売れてしまうの」と うれしそう。
ラベルのデザインもシンプルの中に気品がよい。
わたしもさっそく こくのあるゴマの味を愉しませてもらった。

【写真】岐阜県可児市 兼山1418:「ギャラリー かねやま」にて。
2010/12/16
普茶料理のおけいこ日 (お正月料理) (1096)

( 普茶料理の おけいこ日 )

( 花型レンコン↑ と きんとんのフルーツ和え↓ )

きょうは 普茶料理のおけいこ日。
・・・お正月料理。
「黒豆」「花型レンコン」「きんかん甘露煮」、
「きんとん フルーツ和え」「不老柿」
それに、「松傘ぎんなん」「昆布巻き」「百合根団子の椀物」。
盛りたくさんの品数を 作る。
普茶料理は 手の込んだものが多く、時間がかかる。
「松傘ぎんなん」は、ぎんなんの殻を取り除き、薄皮をつけたまま低い温度の油で20分間も揚げて・・、その後2時間も茹でるという、気の遠くなるっような作業がある。
「百合根団子の椀物(かぶら汁)」も、裏ごしなどの 手間のかかる品。
ところが、試食してみると なんとも言えない、しっとりとした味が口に中に広がり、幸せな気分になる。
これが 苦労のし甲斐がある時だ。
いつも思うが、今回もまた、器と盛り付けの美しさに 眼をみはる。

( 昆布巻き↑ )

( 不老柿↑ )

【写真】 いずれも普茶料理「ギャラリー かねやま」にて。
2010/12/15
冬景色 (1095)

朝、ウォーキングするようになって 一年余り。
だいたい 同じようなところを歩いていると、
四季折々の移り変わりに、より敏感になる。
今朝は 田んぼの多いところに行った。
一見 何の変化もなさそうだが、ここの冬枯れの景色は美しく、
わたしの好きな景色の一つになる。
誰も居ない 凛とした冷たい冬・・。
心も身も 引き締まる思いがした。
きょうも一日 忙しくなりそう。

2010/12/14
施 釉 (1094)

わたしは、ロクロは 家でして、
素焼きと本焼きは 先生に頼んでしてもらう。
先日のマグカップ13個と皿6個の素焼きに、釉がけに行きました。
午後は本降りで、寒い日になった。
そのためか 誰も居なくて、わたしだけでした。
作陶の過程で、むつかしいのは、作品と釉薬との相性です。
きょうは ゆっくり ていねいに、したつもり・・。

(素焼きができた、生徒さんの作品棚)(釉薬の保管棚)



