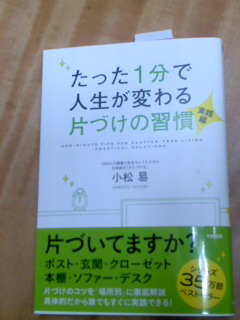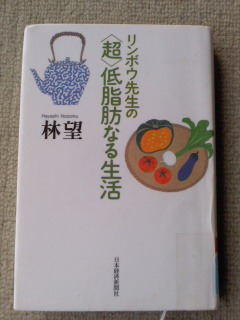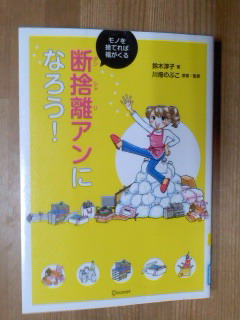2011/02/21
「たった1分で人生が変わる・・」 (1163)
小松 易・著
『たった1分で 人生が変わる 片づけの習慣 -実践編-』
本屋さんのベストセラー5位に 選ばれていた。
わたしは今までに こういう本を何冊も読み、ここに書かれているいくつかは実行している。
* 郵便物の「要る」「要らない」は その場で判断する、とか、
* 「玄関」は すっきりと片づけ、「ゆとり」を 持っている。
* 下着類は 数を決め、1枚捨てたら 1枚買う」とか。
でも、まだまだ 片づいて いません。
この本も買わなければ 一冊分片づいたのに、と思いますが・・。
わたしの場合、雑誌類は買って読み終えたら、娘たちに回したあと、処分してもらうので、ほとんど溜まってません。
【写真】 『たった1分で 人生が変わる 片づけの習慣 -実践編-』
小松 易・著 2010.12.18.第1刷発行。中継出版・刊。@1300e
2011/02/20
尾張富士へウォーキング (1162)

上天気です。
進学も決まり、卒業式を待っている高校生の孫を誘い、尾張富士へウォーキングに行く。
ところどころに句碑が立っているので、読みながら歩くと楽しい。

せっかく歩いたのに・・・と言いながら、
帰りにコーヒーを飲みに喫茶店に。
モーニングサービスにオムライスが出てきてびっくりした。
愛知県はモーニングコーヒーに、パン、卵、ヨーグルト、おにぎり、茶碗蒸しまででてくるところもある。
この店も10時半まではモーニングのサービスが出るようだ。

2011/02/19
『 リンボウ先生の 超 低脂肪なる生活 』 林 望・著 (1161)
著者の林 望(はやしのぞむ)先生は ケンブリッジ大学の客員教授を歴任されて、イギリスに関するエッセイや小説家として 名高い。
わたしも学者さんとしての本を読ませていただいている。
最近 ダイエットの本に紹介されていて、料理をされることを知った。
2004年に滞在先のロンドンで、人生二度目の急性胆のう炎という病気にかかり、その激痛に苦しんだ。あんな痛いのはもう御免だ。そのために このような低脂肪を中心の料理を続けられるように なった。
自分で食べるものを研究し、料理をされる。また食材の栄養素を、うま味をどうしたら引き出せるかを 実によく知っておられる。
と言うより、徹底して考えられたよう・・。
林流 「超」低脂肪の格言は「インテリジェンスと多少の我慢」。
わが家では 家族の好みなどもあり、すべて先生のようにはいかないが、参考になるレシピや食習慣が 盛りだくさんある。
ダイエットしたい人には、超おススメの一冊。
ただし 怠惰に流れてしまう人は ダメです。
【写真】 『 リンボウ先生の 超 低脂肪なる生活 』 林 望・著。
日本経済新聞社・刊。2005.12.19.1刷。@1500e
2011/02/18
藤工芸の けいこ日 (1160)
先月からの 羽子板作り。
台のほうは 先月 作ってあったので、
今月は 松や椿の花を編んで、セットに組んだ。
2時間半の けいこの時間は、あっという間に終わってしまう。
先生が いつも コーヒーやお菓子を用意してくださり、
テータイムもあり、おしゃべりも愉しい。

2011/02/17
「本とは 何ですか?} (1159)
本とは 何ですか?
韓国に 孔技泳(コンジヨ)という作家さんがいる。
この本を読んでいて抜粋したことば・・:
(私たちの幸せな時間)
『※ あなたにとって 本とは 何ですか?』
『※ 一万ウォンで買える、もっとも価値あるもの。』
・・・一万ウォンは、日本円では800~900円くらい。
『※ 本には お金で買えない夢があり、希望がある。満足感がある。』
・・・・・これには、わたしも 同感だ。

【カット写真】五条川の川面に 鴨の家族が・・。
2011/02/16
心配りの行き届いた店 (1158)
最近 お気に入りの珈琲ショップがある。
(1) 喫煙者と そうでない人の 席を分けてある。
( お店が広いから できることだけど )
(2) ウェイトレスは 落ち着いた年齢の人が多く 言葉使いがていねい。
(3) 電話がかかってきたとき、電話を取るとすぐ「お電話をありがとうございます」と言われる。
当たり前のことだが、なかなかできない人が多いので・・・・、
この店は 社員教育が よくできている、と思った。
珈琲の味も よく、器類も、まあまあ私好み。

2011/02/15
池田勇人元首相 (1157)
2月10日日本経済新聞の夕刊を開いて びっくり。
( 「女が語る 政治の家」:6面 )
写真は池田勇人氏の奥様(満枝夫人)かと思ったら、次女の紀子さんだった。 目もとが母上そっくり。
わたしは40年以上も前に、当時総理大臣だった池田家に、信濃町のご自宅へ伺った。
同じ学校の先輩であり、友人の母の友達でもあった満枝さんに お目にかかった。 1時間余り おしゃべりを楽しんできただけだが。
玄関脇に 記者さん用にトイレがいくつもある建物だけが新しくて、母屋などは旧い家のように記憶している。
池田勇人首相は、所得倍増論を唱えた指導者。
(貧乏人は麦飯を食え、と言ったとかとも伝えられるが)
わたしは、池田総理を超える首相は、最近 出て来ないなぁと ひそかに思っている。

【写真】 日本経済新聞 2011.2.10.夕刊(6面)
2011/02/14
『 わたしが旅から学んだこと 』兼高 かおる・著 (1156)
『 わたしが旅から学んだこと 』兼高 かおる・著
~80過ぎても「世界の旅」は継続中ですのよ!~
テレビ放送「兼高かおる 世界の旅」(TBS系)。
1959年伊勢湾台風の年から 31年間も続いた。
この放送が終了してから、20年にもなる。
時々想い出してはいたが、本書を見つけ、なつかしく すぐに読んだ。 久しぶりの著作であるとか。
この番組を よく観て、わたしも「(外国を)観てみたいなぁ」と思った。
わたしが ほんのわずか(10カ国くらいか?)の外国を見る機会のきっかけにもなった。
兼高さんは150カ国もの国を回り、人生を謳歌し、83歳の今もなお、若々しい精神の持ち主で、冒険的な生活を過ごされている。
このような著者が書かれたものだから、おもしろかった。
著者は死ぬまで、退屈とは無縁の女性(ひと)。
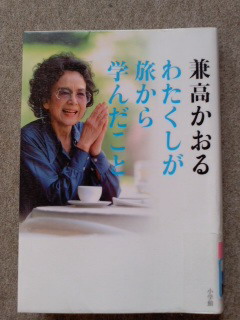
【写真】 『 わたしが旅から学んだこと 』 兼高 かおる・著
~80過ぎても「世界の旅」は継続中ですのよ!~
2010.9.6.初版第1刷発行。小学館・刊。@1500e
2011/02/13
「断捨離アン」になる むつかしさ (1155)

断捨離アン(ダンシャリアン)になるのに、
一番のネックは「本」と、もうひとつ「陶器」がある。
本は安いので 捨てようと思えば捨てれるが、
わたしの場合は 生きていくのに 本は無くてはならないものだ。
陶器は 自作のものは まあ 捨てれる(よほど お気に入りのもの以外は)。
父親から もらってきたものは 捨てられないし、子どもたちにも 残してやりたい。
また、わたしが好きで買った韓国の青磁類、日本の窯元で買い集めたものは、やっぱり死ぬまで置いておきたい。
と なると、断捨離も わたしの場合は なかなか むつかしい。

2011/02/12
『 断捨離アンになろう! 』 (1154)
『 断捨離アンになろう!』~モノを捨てれば福がくる~
鈴木淳子・著 川原のぶこ・原案・監修
「読みたい!」と言ったら、娘が貸してくれた。
「断捨離」がブーム。
”ダンシャリアン”火付け役のエッセイとコミックからなる本。
『
断 ――― 不要なモノが入るのを 断つ。
捨 ――― 不要なモノを捨てる。
離 ――― 片付けやモノへの執着などの 煩わしさから離れる。
これを実践してスッキリ気分良く「とにかく日々ご機嫌で過ごしましょう」という。
』
わが家と言うより わたしも モノを捨てられない。
大きな理由を考えてみた・・・
「モッタイナイ」「高価だったから」「想い出のものだから」。
この「断捨離」を知った一年半くらい前からは、買うときはこの言葉が浮かんでくるようになった(ほんの少しだが・・)。
わが家の一番の悩みは「本」。
どの部屋にも 床が抜けると言われるほどある。
捨てても捨ててもそれ以上に、わが家にやってくる(家族全員が 本 大好き)。
この本を見ながら 一番気になったのは「いつ死んでも大丈夫か?」。
「自分は納得いく人生を送っているか?」これはYESと言えるが、「いつ死んでもよい準備はできてるか?」と言われたら 全然できてないのだ。
明日から身辺をきれいにして、「ゆとり」を持って 輝いて歩いて行けれるように、「”死活”」を 始めようかしら・・。自信は無いのだけれど。
【写真】 『 断捨離アンになろう! 』~モノを捨てれば福がくる~ 鈴木淳子・著 川原のぶこ・原案・監修。
2010.12.10.第1刷。 @1200e
㈱デイスカヴァー・トゥエンティワン・発行
*************************
「断捨離」はクラター(ガラクタ)コンサルタントのやましたひでこさんが「執着から離れる修行を実践しよう」と提唱する。