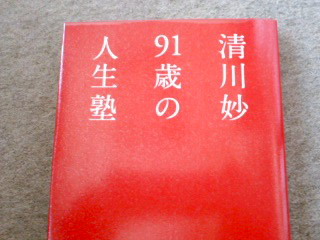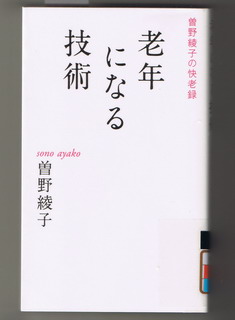2012/10/23
『 つるかめ助産院 』 (1673)
小川糸・著 『 つるかめ助産院 』 集英社・刊
つい最近 NHKでドラマ化され放映されていた。
わたしは知らなくて、最後の第8話のみ 見た。
本屋さんでは『 つるかめ助産院 』が何十冊も積まれていた。
『 食堂かたつむり 』と同じ作者だが、作風はずいぶん異なっていた。
わたしは三度 妊娠出産という体験をしたが、遠い昔のこと。
本書を読みながら、少しは思い出してなつかしい感情を愉しんだ。
それにしても小川糸という作家は、食べ物にも興味があるのか、描かれている食事が めちゃおいしそうだ。
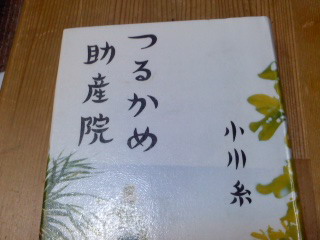
【写真・部分】 小川糸・著 『 つるかめ助産院 』 集英社・刊
@1400e
2012/10/21
あかりアート展 (1672)
岐阜県美濃市で 毎年開かれる「美濃和紙あかりアート展」へ行ってきた。二年ぶりった。
美濃市は 美濃和紙と「うだつの上がる町並み」で有名。
国選の伝統的な建造物が多くある。
古民家利用の食事処、カフェや 美濃和紙の店などがあり、散策も楽しい。

夕方5時。
町並みの道端に並んだ、500点以上もの「美濃和紙あかりアート」に点灯されると、見物客から「わぁ~ きれい!」と声が上がる・

ひとつづつ見て歩く。
6時ごろになり、そとはさらに暗くなると 灯かりが美しく輝く。
一緒に行った小学生の孫も「来年は小学生部門で出品しようか・・!」
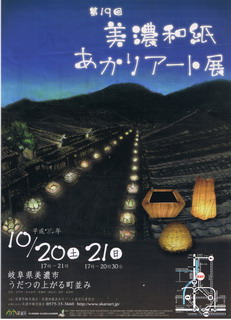
2012/10/20
史跡:東之宮古墳に (1671)

秋晴れの日
史跡:東之宮古墳へ。
友人に頼んで 案内をしてもらった。
成田山名古屋別院の奥で、
やはり一度は連れていってもらわなければ 登り口も わからなかった。
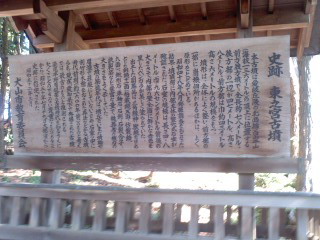
愛知県下で一番古い 大きな古墳だ。
今日も 何人かの人が 手入れされていた。

そのあと モンキーパークへ行き、世界の猿を見学。
わたし達、おばあさんのグループは見当たらないと思ったが、
そうでもなくて 楽しんでいる方も 多かった。

2012/10/17
電子レンジで煮物? (1670)
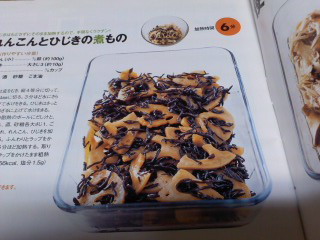
娘から借りたオレンジページ(2012年8月17日号)。
特集は「レンジで超ラクごはん」。
ひじきとレンコンの 煮物を作ってみた。
レンコンをうすく切ったものと ひじきは、サーッと水洗いし、水気を切ったものを用意する。
耐熱のボウルに だし汁と しょうゆ、酒、ごま油を入れ、ラップを掛け、電子レンジで加熱するだけ。
火加減を調節しながら煮る という智恵も要らないし、細やかな味の感覚も無いが、簡単で まあまあの味でした。
若い人たちの読む雑誌も なかなか おもしろい。

2012/10/16
『 91歳の人生塾 』 清川妙・著 (1669)
91歳になっても、著者のように老いを怖れない心の持ち方、日々のありようを読ませていただいた。
著者・清川妙さんの本は、いままで何冊も読んだ。
考え方も若いし、なによりも年老いても海外に一人で出かけられたりするので、健康に恵まれた方でもある と思っていた。
著者にならって、いくつになっても挑戦する気持ち・勇気を持って 生き続けていきたいですね。
【写真・部分】 清川 妙・著 『 91歳の人生塾 』 小学館・刊
2012.8.29.初版第1刷発行 @1300e
2012/10/14
新聞小説 (1668)

日本経済新聞夕刊の新聞小説は、重松清・著の「ファミレス」。
アラフォ世代の 何組かの家族の、日常生活を描いたもの。
子どもが独立したあとの、また 二人きりになったとき、
夫婦はどのように過ごしていくか、というのが問われている。
10月13日(土)のところで おもしろいことが書かれていた。
・・「オシドリってね、毎年パートナーを替えてるのよ。
だから、あんなに仲良く寄り添って池に浮かんでるの」
えっ 本当!? と思って調べたら、正しかった。
「Kさん家は オシドリ夫婦ね」というセリフを言うとき、
ちょっと考えてしまうなあ・・。
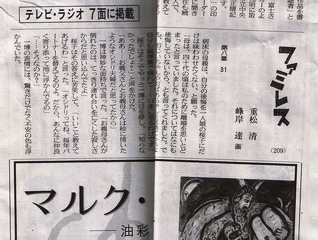
2012/10/13
「そらいろめがね」 (1637)
友人が スーパーでの「手作り展」に参加している。
袋物、ショール類、帽子、アクセサリーなど。

それに加えて「揚げパン」のコーナーも。
これはライトバンを改造したパン屋さん。
「そらいろめがね」という名前。

ミニバンの中には、コンパクトなミニの台所があり、
注文すると パンを揚げてくれる。
シナモン、きな粉など 好みの砂糖をまぶして出来上がり。
ふわふわして とってもおいしい。

愛嬌の良い、若い男性がこれを始めて2か月だとか。
わたし達 おばさんに 好印象でした。

2012/10/11
藤工芸 (1636)

きょうは ついたてに飾る小さな花を編む。
小菊を10本、ねこじゃらしを10本、
とりあえず 編む。

最近は 陶と藤のコラボ作品を制作されているの。
わたしは 皆さんの陶のほうを 作らせていただき いそがしい。

2012/10/10
『 老年になる技術 』 曾野綾子・著 (1635)
こういう本が目につくようになった。
著者・曾野綾子さんの本の中から
「老年になる技術」のことばを選んでまとめたもの。
いくつかは 気に入った。
が、一番共感したのは、
「いささかの無駄、愚かさを許して」と題して、食欲も物欲も無くなったら終わりだから、いささかの無駄や愚かさは覚悟の上で自分に許したほうがいい、という。
わたしの生き方は無駄ばかりかも知れないが、
人に迷惑はかけていない。
こうした生き方は自分自身のことだから、
安心して過ごせれば それでよい人生だ、と思っている。
【写真】 曾野綾子・著 『 老年になる技術 』 海竜社・刊
2012.8.29.第1刷発行 @880e
2012/10/07
明治村で学ぶ (1634)

市民総合大学 明治カルチャー史学科 の一日目。
「近代和風建築の世界」というタイトルで、
博物館明治村館長の 鈴木博之先生が講義。
明治のころの名人の作品と言われる建築物を、スライドで見ながら 説明を聞く。
わたしは和風の床の間、天井などに興味があるので、熱を入れて聞いた。
講座の会場は三重県庁舎ということで、北の駐車場から歩いて20分! まだ汗ばむので、皆さん会場に着くと汗を拭いておられる。
それでも明治村は きらびやかさはないが、おだやかな雰囲気で 歩いているだけで 気分がよい。
今年も 年間パスポートの書き換えをしてきた。