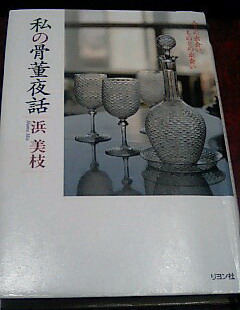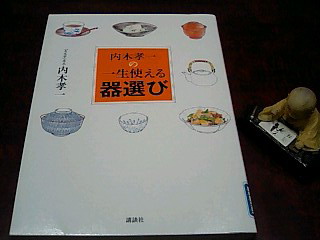2009/04/22
町の空気を吸いたくて
誘われて名古屋に買い物に行ってきた。
中心街・栄町あたり 東急ハンズで 桐の花台。
地下街で 服と日傘、夫のワイシャツと孫たちの靴下などを買う。
どこでも手に入るものだが、なんとなく町に出て買い物して、
都会の雰囲気を味わうと新鮮な気分になる。
いくつになっても、元気に出歩くことも大切だと思う。
何十年前 毎日のように栄町を歩いていた頃とは、空気もちがう。
ランチは アーバネット名古屋ビルブロッサの「豆家茶寮」。
堀りごたつ席個室で 落ち着いた席。
豆腐は 愛知県高浜産の豆を使用しているとかで、
汲み上げどうふ御膳、とっても 美味でした。

2009/04/21
旬を食す (たけのこ

朝市で 朝採りの たけのこを、2本買った。
さっそく皮をむくと 半分くらいになるので、
圧力なべで ゆでた。
新鮮なので、刺身で食べたら 風味がよかった。
「タケノコご飯」が好きな孫がいるので、喜んでくれた。
残りは 明日 ワカメと煮ようかなぁ。
おいしい料理とは、季節の素材を生かして、
シンプルに 作るに限る。

2009/04/20
鉢カバー

「鉢カバー」を作陶した。
黒ミカゲの土に、弁柄で少し模様をつけた。
藤で手を付けたら、少しは 見栄えがした。
知人が「苔玉」を置き、まわりに石を置いて、
コーディネートしてくれた。

2009/04/19
家庭菜園の さやえんどう
ゴールデンウイークが近づくと「さやえんどう」が採れる。
花は 赤い花と 白い花の両方だが、
どうちがうのか よくわからない。
ことしは、種まきを早く蒔いたか、気候のせいか、
もう 食べられるように育った。
花はつぎつぎと咲き始め、なる時季も短いので、
えんどうの収穫はいちどに採れる。
一時季は 毎日のように食卓にのぼるので、
孫たちには 飽きられます。
卵とじ、野菜炒めにも おいしい。
緑の鮮やかさ ほんのり甘く歯ざわりの良さが魅力の野菜。

2009/04/18
キッチンガーデン

花壇の片すみに蒔いた 三つ葉が、ものすごい数で出てきている。
いちど蒔いたら 何年間も、次から次へと出てくる。
グリーンアスパラも、食べられる大きさになってきた。
「春の野草(野菜)には、人間の生理代謝に欠かせない成分がバランスよく含まれていて、冬に溜め込んだ老廃物などを解毒してくれる」という。
・・・料理研究家の辰己芳子さんが よく言っておられる。
自然界というのは、本当に「すごい!」と思う。

2009/04/17
大失敗 (藤工芸教室)

きょうは藤工芸のおけいこ日。
先生に頼まれていたものを忘れないように!と、そればかりを気にしていた。
朝、ゴミ出しの日でもあり、バタバタして9時前に 出発。
到着して、さて 材料と 作りかけの作品の入ったカバンを探したが 無い!
うちの玄関から、車に載せた覚えがない。
なにをしてるんでしょう・・ わたしはがっかり。
先生は、じゃあ こちらを先にしましょう・・と とりなしてくださった。

Photo////// 090416-1110-0001 「じゃあ こちらを先にしましょうか・・」とやさしい、藤工芸教室の先生
2009/04/16
『私の骨董夜話』 浜 美枝・著
浜 美枝・著 『 私の骨董夜話 』
(人との出会い、ものとの出会い) リヨン社・刊
この本を読むのは 2回目。
女優としての浜 美枝さんは どんな仕事をしているか、まったく知らない。
映画も観たことが無い。
わたしの知る浜 美枝さんは、骨董蒐集家としてである。
うらやましい才能というか、美を見る眼の確かさに驚く。
本書に出てくる数々の骨董は、いずれも一流品ばかり。
浜さんは、宝の持ち腐れでなく、使用して生かしているところは えらい。
【写真】浜 美枝・著 『 私の骨董夜話 』(人との出会い、ものとの出会い)リヨン社・刊 2005.4.5.初版発行 発売:二見書房 @2300e
2009/04/15
小さな花びん ( 新作 2点 )
わたしは花器、それも鶴首が大好き。
いっとき鶴首ばかり 練習していた。
いまは洋風の家が多くなり、花器もかわいい変形のものが似合う。
きょうは 新作を 2点。
ひとつは、ケーキの函の横を切り取って、型紙にしていて、
後ろ側に小さな筒状の器がくっ付けてある。
これに水を入れて、花を活けられる。
もう一方は、あるコーヒーショップのトイレにあった、
小さな花びんからヒントを得て、自分なりに作ってみたもの。
きれいな花を入れるので、
焼き〆にしようかなぁ・・。

2009/04/14
『 内木孝一の 一生使える器選び 』
うつわのみせ「大文字」店主 内木孝一・著
『 内木孝一の 一生使える器選び 』 講談社・刊
「ご飯は左、汁は右」に置くもの。
これは主婦なら誰もが知っている。
だが、どうして・・ということは、わたしは知らなかった。
これは鎌倉時代半ば、道元がお坊さんたちに向けて食事作法を説いた「赴粥飯法(ふくしゅはんぽう)」という本にも書かれているとか。
ご飯が左とされたのは、日本では左の方が尊ばれたから。
主食であるご飯の方が、格が上。
そこでご飯が左、汁は右となった。
本書は京都の老舗陶器店主・内木孝一氏が、
盛り付けやテーブルコーディネートのこんなポイントまで教えてくれる。
器好きの人には うれしい本。
【写真】「うつわのみせ 大文字」店主 内木孝一・著『 内木孝一の 一生使える器選び 』 講談社・刊 2008.8.28. 第1刷発行 @1400e
2009/04/13
日本語教室
市内に住む外国人に日本語を学んでもらおうと、支援がはじまっている。
わたしもボランテイアで お手伝いをしている。
何年か生活していると、「話すこと」はできるようになるが、
「読み」「書き」ができない。
この日わたしが受け持ったひとたちは、全員「日本語はむつかしい」と言っていた。
がんばって 勉強してネ。