2009/07/01
しらひげ神社 (八百津町)

木曽川学の講義のとき、先生から聞いて、自分の目で見てみたかったので、岐阜県 八百津町の白鬚神社に行ってきた。
わが家から一時間ほどかかる。
八百津町には 久田見に「白鬚神社」と、野上に「白髭神社」がある。

同じく「 しらひげ 」と言うのだが、漢字では、
久田見の白鬚のほうは アゴヒゲ を表記し、
野上の白髭のほうは クチヒゲ を表わす。
どうしてかなあ?
久田見の白鬚神社は、高さ40㍍、幹囲6.8㍍の樹齢300年以上の杉の巨木があった。

2009/06/30
ハンゲショウ (半夏生)
ハンゲショウ(半夏生)の花が咲いた(ドクダミ科多年草)。
ずいぶん前に友からいただいて大切にしているが、
なんだか今年は数本しかなく さみしい。
先端の二、三枚の葉を白化させている。
知らない人が見て「これ 病気?」と言われた。
花が終わると緑色に戻る。
ふしぎな 花。

2009/06/29
第4回木曽川学セミナー(流域の民俗・信仰)
本日のテーマは木曽川流域の民俗と信仰。
講師は岐阜市立女子短大の須永 敬 先生。
長いあいだ、生きてきて、
川の景観は いいものだなあと感じた以外は、
あまり関心がなかった。
きょうの先生は 川と民俗の関係を やさしいことばで話してくださる。
「川を知ることが 日本の文化を知るツボです」と言われたこと、
とても分かりやすかった。
帰路、木曽川流域を 車で走りながら、
あらためて 川を見直した。

2009/06/28
織物に 初挑戦

友人に 織物の上手な人が居る。
きれいなマフラーやベストができるのを、
うらやましく 見ていた。
お宅に伺って 教えてもらう。
最近の織り機は 軽いので びっくり。
たて糸をかけてもらって、横糸を赤とグレーで模様を入れていった。
細かく目を数えることともなく、自由に編んでいけるので、
おもしろくて 止められない。

2009/06/27
藤工芸教室 ( 皿。お人形 )

藤工芸教室。
月に1回の生徒さんが多い。
わたしは月2回 お願いしている。
藤はカゴ というイメージが強い。
きょうは 3種類の編み方で 木の葉型の皿を編む。
一本の藤から いろいろな工芸品に出来上がるのが すごい。
下の人形は、先生の作品。
それぞれ表情が豊かで、とても かわいい。

2009/06/26
ベランダ クリーン サンダル
韓国ソウルで 友人Cさん宅に泊まったとき、
風呂場やトイレで使っていた。
うすいピンクや白で きれいだったので、いいなあと思っていた。
日本では何年間も見なかったのが、ホームセンターで見つけた。
「ベランダ クリーン サンダル」 このデザインでこの色しかない。
中国製だとか MADE IN CHINA。
ソールの全面に穴が開いている。水が溜まらないので ベランダで雨に濡れてもよい、と書いてある。
夏の間 便利に使えそう。

「ベランダクリーンサンダル」輸入発売元(広島市)アイメディア㈱
2009/06/25
メラミンスポンジ

さて これは 何でしょう??
4cm角の 白いキューブ。
なんてきれいで、可愛いこと。
これは 水を含ませるだけで、こすれば汚れが落ちる。
ステンレスの流し、タイル、器などなど。
ステンレスの風呂オケやタイルの床の水あかにもバツグン。
茶シブも よく落ちる。
いままでは、大きいものを買ってきて、自分でカットしていたが、
これは 便利・・。
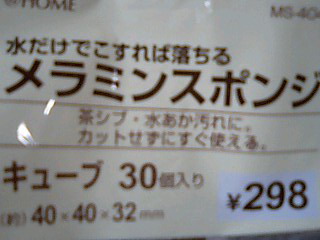
2009/06/24
赤シソ 不足
午後 買い物に行く。
赤シソが無いので、店員さんに聞く。
「ことしは赤紫蘇が不作で あまり入荷しない」。
「朝、1、2時間で 売切れてしまうので・・・」。
翌日、9時半に行って 買ってきた。
黒っぽいシソが 見る見るうちに、
紅色になっていくのを見て、
孫が「わたしもやりたい」と。
この子は幼児なのに、梅干しが大好き!

2009/06/23
ふくろう作陶
Mさんにたのまれて「ふくろうの 灯かり」を作っている。
赤土で作り、焼き〆、還元焼成しようかなぁ。
レンガ色で落ち着いた色にしたい。
前面は顔があり、穴を開けないで、後ろ側は全体に開けた。
ふくろうは「不苦労」などという語呂合わせで、
ラッキーシンボルとして 好まれる鳥。

2009/06/22
とうもろこし
知人から 採りたての「とうもろこし」をいただいた。
家庭菜園でとれた 初ものです。
2月に種をまき、虫が来ないように、二重のビニールのトンネルを架け、丹精込めて 作られた。
ゆでて、素材の食感そのまま 楽しみました。
かじりだしたら やめられません!
甘くて とってもおいしかった。 ごちそうさま!



