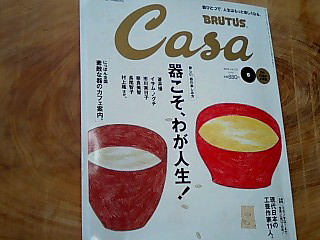2010/05/07
東京みやげ 「 ごまたまご 」

東京みやげ!と言って東京玉子本舗たまやの「ごまたまご」をもらった。
そのときは気がつかなかったが、食べるとき「ごまたまご」って、どこかで聞いたことがあるなぁ・・。
民放ラジオでよく「ごまたまご」が3時をお知らせします、と言っているのを 思い出した。
コマーシャルって、このように意識しなくても 覚えてしまうものだ。
「ごまたまご」は、中に黒いゴマが詰まっていて、こくがあり、紅茶のお茶うけに おいしかった。

2010/05/06
またまた 黒い野菜

連休中に 小さな家庭菜園に植える苗を買いに行った。
天気も好く、気温も上がり、苗屋さんは大にぎわい。
トマトの苗のところを見て、
「えっ トマトまで黒?!」
トマトの真っ赤なイメージはどうなるの。
トマトよ おまえも黒か。

2010/05/05
扶桑町吹奏楽団

隣町の吹奏楽団に高校生の孫が入団している(トロンボーン)。
この子は学校でも吹奏楽部で 毎日 練習がきびしい。
そのうえ金曜日は隣町での練習がある。
その日は学校から帰ると食事する間もなく、車の中でおにぎりを食べながら、隣町の練習に参加している。
聞くところ、高校生から60歳近い人まで、幅広い年齢の人が、チームワークよく演奏されていた。
孫も熱中できるものがあっていい。
わたしもできることは協力してやりたい。

2010/05/04
ゴールデンウイークは?
ゴールデンウイークは お天気に恵まれた。
外孫も遊びに来たので、庭でバーベキュー。
わが家ではこの“外食(そとしょく)”が好きで、寒さの和らぐ4月から9月までは、よくやって楽しむ。
今夜は魚釣りに行ってきた人から、「さごし」の大きなのをもらったので、これも焼いてみたら、とってもおいしかった。
炭火の優しい火加減で、にぎやかな、おいしい夕飯でした。

2010/05/03
器まつりに

( 「器まつり」 古城 兼山城のふもとにある兼山窯。 )

古城 兼山城のふもとにある兼山窯に、
「器まつり」に行ってきた。
実は何年か前、この器まつりに来て、作家先生の奥様が普茶料理の先生ということで、さっそく弟子入りした。
あれから3年経った。
ちょうど昼どきになり お客さまも帰られ、わたしたちだけになったので、ご夫妻も手がすいて、友人と4人でおしゃべりに花が咲いた。
ご主人の器も品がよく、使っても飽きがこない。
シンプルの中に色気が感じられて、料理のおけいこにもたっぷり使わせてもらっている。
奥さまのほうは、ガーデニングの指導者であり、テーブルコーディネートの達人でもあるので、いつも参考になることがいっぱい。
きょうは器好きの友人と一緒なので、長い時間お邪魔していた。
上天気でもあり、兼山の緑が借景に、花が咲き乱れ 美しい空間に満足。

( 「兼山窯」器まつり )

2010/05/02
たけのこ

今朝 早く、知人から「たけのこ」を6本もいただいた。
「昨日 掘ったのだから、早くゆでてください」と言われ、
米ぬかを買いに走った。
(米のとぎ汁でもよいが、量が多かったので)
タケノコは「古事記」に出てくるほどで、
日本では 古くから食べていたようです。
わが家も建て増しをした部分は、もと、竹やぶだった。
20年前は たけのこが採れて、たくさん食べていた。

2010/05/01
カフェ・ガジュマル
”カフェ ガジュマル”
知人と昼ごはんに 新しいカフェに行ってみた。
城下町通りで、旧い民家をリフォームした店。
カフェの奥は、ギター工房が併設されてる。
マスターは「鹿児島出身なので、名前をカジュマルとしました」と。
若いが しっかりとして とても感じのよい方。
ランチのサンドウィッチも おいしかった。
また、行きたい店。

「カフェ・カジュマル」犬山市犬山 東古券661
Cafe Gajumaru TEL 0568-65-9093
2010/04/30
柳生 博・著『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』
柳生 博・著 『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』 講談社・刊
八ヶ岳倶楽部へ時々行っていた頃(10年以上も前)は、近くの町より八ヶ岳の道のほうが詳しいぐらいだった。
一緒に行った友は 鬼籍になり、八ヶ岳にはすっかり行かなくなった。
その頃『八ヶ岳倶楽部 森と暮らす、森に学ぶ』を買って読んだ。
昨年、『八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森』が出版されたのを読み、写真を見て、木の育った様子にびっくり。
著者の柳生博さんや奥さま、息子さんたちは、八ヶ岳倶楽部でお会いできると、にこにこと とても優しい笑顔で、気さくにお相手をしてくださっていたものだ。
今回この著者のプロフィールを見たら、84歳になられたとか。
わたしが今、木彫りが好きなのは、この八ヶ岳倶楽部でよく拝見していた 田原良作の作品の影響です。
久しぶりに八ヶ岳へ行ってみたいなあ と思いながら、読んだ本。
柳生 博・著 『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』 講談社・刊

【写真】柳生 博・著 『 八ヶ岳倶楽部Ⅱ それからの森 』 講談社・刊 2009.8.7.発行。@1600e
2010/04/29
初めて見た サヤエンドウ
鮮やかな緑色と、歯ざわりのよい えんどう。
毎年、食べきれないほど収穫できるのだが、
ことしは手入れ不足で 全滅状態。
2、3日前 一宮市の公園に、
黒紫色の実がなった さやえんどうがあった。
この色は 初めて見た。
オランダ、台湾からきた品種のようだ。

2010/04/28
毎日ながめてる本
『 Casa カーサ 』5月号(マガジンハウス)は、
特集「器こそ、わが人生!」。 さっそく購入した。
村上隆、広瀬一郎の対談「今 陶芸がおもしろいわけ」が おもしろかった。
現代の器のネタ元は、魯山人だと言う。
料理に合う器を作ったり、コーディネートしたりする発想は、魯山人からだと。
そういえば近頃は テーブルコーデイネート、器と花のコラボを楽しむ人が多くなったように思う。
時どき 『Casa』を出して、ページを繰って ながめている。
【写真】 『 Casa BRUTUS 』カーサ・ブルータス 2010年5月号。
マガジンハウス;月間版(2010.4.10.) 2010.4.10.発売。@880