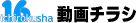18 行革の本丸教育改革と民主党との出会い
さていよいよ父から君に伝えておきたい最大のテーマ教育について語ることにする。
そもそも私は大学進学の時教師になりたくて、教育大学を受験したがそれは失敗に終わった。だからもともと教師とか教育に対する一種のあこがれは持っていた。また政治家になり座右の書となった、論語を読むようになり、孔子という人は「人類の教師」と呼ばれ、結局は政治家を教育した人であることを知り、政治家と教育者が重なった。さらに、犬山市長になったときドイツを訪問し、ドイツ語で市長のことをベルガーマイスターと呼びその言葉の意味は、市民の先生であると知った。
「よし、俺は学校の先生にはなれなかったが市民の先生になれたのだ。この仕事に徹してやろう」思い立ったのがそもそも教育行政に心血を注いだ所以である。
まず県議当時からの畏友瀬見井久さんを教育長に抜擢した。その時の口説き文句は「俺の諸葛孔明になってくれないか」だった。彼は愛知県庁で企画畑を歩いてきたいわゆる行政プランナーである。議員にもずけずけものをいうしマスコミ、文化人に広範なネットワークを持っていたのでそこに目を付け、普通の教育者ではできない教育改革に挑戦したかった。彼は教育界にしがらみがなくまた性格的にも多少奇人に近いのではないかと思うくらい安易に妥協しない一徹な人物だった。そこを私は買い、狙いどおり当たった。
まず言っておくが、教育論は難しい。丁度人生論が百家争鳴のごとく、実は教育論も顔が違うように千差万別なのだ。だから、教育論は抽象論ではなく、具体的な政策として提示することが大切だと思う。教育改革の具体策は少人数授業からスタートした。ときどきこう言う人がいた「昔学校の授業は1クラス50人以上で平気にやったものだ、今の子供は授業中も騒がしく集中力がない、そもそも教師の出来が悪いのだ」と。歴史を逆戻しなんかできるものか!子供を取り巻く社会も生活環境も激変している。現在の授業風景の問題を解決するためには、1クラス30人程度の少人数にして、教員が一人一人の子供とより丁寧に接することだ。それが少人数授業の意味だ。
この「少人数授業の理論」を教えてくれたのは、民間校長に迎えたかった中京大学の杉江修二さんだった。私は選挙の時の演説会を思い出し、大勢の演説会より少人数のミニ集会のほうがはるかに効果的であることがわかっているから、少人数授業の効果を一瞬にして理解した。
少人数授業は当然のことながら教員の数が増え、その増加コストはどこが負担するのかという議論に発展する。公立学校の教員は市立の小・中学校でも全員が都道府県の公務員であるから原則的には愛知県の問題である。初めのうちは犬山市単独で負担していたが、この費用負担の問題を愛知県及び国の教育行政のテーマに投げかけてみた。このあたりから、犬山の教育が全国の注目を浴びるようになる。これこそが地方分権の具体的な実践である。
そもそも教育行政は複雑怪奇だ。義務教育の小・中学校教員の身分は市町村長の管理下に置かれ、人事権は県の教育委員会が持ち、給料負担は国と県で分け合い、授業の中身は全面的に国の学習指導に縛られるなどなど、いったい責任者は誰なのか、どこで教育の責任をとるのかわけがわからないではないか。
そこで私は犬山市の教育関係者とひろく市民にこう呼びかけた。
「犬山の子供は犬山で育てよう!」と。この言葉は市民の人口に膾炙するところとなり、教育に熱心なまちというイメージが浮上するきっかけとなる。
少人数授業の重要な切り口は、単に子供の数を少なくするというだけでは決してない、少人数に伴う諸条件を整えること、いわば「少人数授業文化」を作り上げることである。その一環としての教科書を犬山市独自で作る政策も、犬山の教育改革の名を高からしめた。これも、私の中学時代、漢文の先生が一度も教科書を開かず授業し、それが実に魅力的だったことを思い出し、お仕着せの教科書など無意味だと思い、独自の教科書を作る企画に市長として財政支援した。
教科書は授業を構成する大事なツールだ。私はそもそも教科書の国家検定など反対論者である。教科書は教師が自分の一番好きなものを使えばいい、自分の言葉で語らずして子供に伝えたいものが伝わるわけがない。
私と犬山市教育委員会と現場の教員たちとのコンセンサスは、真の学力は外から強制的に押し付けて身につくものではなく、内発的に、子供自身が自ら掴み取る状態を作ってやることによって獲得されるというものであった。楽しさこそ学びの最大のエネルギーとなる、という思想だった。「学んで時にこれを習う また喜ばしからずや」人類の教師、孔子も「論語」の書き出しで弾んだように学ぶ楽しさを述べているではないか!
「Education」という英語を「教育」と翻訳したのは福沢諭吉だが、これは、「学習」と翻訳すべきであったという論もある。教えるという外からの視点より、学ぶという内からの視点に重点を置くべきである。
わたしは全国で最も学校現場に足を運んだ市長だと思っているが、現場の教員たちには多くを教えられた。教員にはもともと子供に何かを伝えたいと思う強い「教師魂」を持っている人がいた。もともと教育というものは親が子供に直接教えたものだ。それが世の中忙しくなり、親たちは自分に代わってその行為を公の学校と職業としての教員に任せたのだ。親が教員を信頼しなければ、公教育というものは成り立たない。少人数授業に端を発した改革についてその他いちいちここでは述べないが、手法は多岐にわたった。
ただ私の言えることは犬山の教育改革は、どちらかというと市民サイドではなく、現場の教員サイドに立った改革であり、教員の潜在力「教師魂」を引き出すための制度改革にウエイトをおいた。
当時、教育論議は地方分権論の中で盛り上がりを見せ、特に教育委員会の在り方が賛否両論かまびすしかった。教育委員会制度というのは戦後アメリカから直接民主主義を表すものとして導入されたのであり、その精神は地方分権の時代にふさわしい民主的なものであるにもかかわらず、文科省の中央集権的手法が教育委員会制度を空洞化していた。私は、教育委員会は上意下達の統治のためにあるのではなく、現場の教員たちの教育という行為を支援するための装置であるという、「教育委員会擁護論」を展開した。 この主張は中央にも伝わり、まず文科省の諮問機関である中央教育審議会委員となり学習指導要領の審議に参加した。その後、民主党に呼ばれ教育政策会議で話をすることになった。この時の民主党代表が前原誠司さん、政策会議の座長が仙石由人さん、民主党とのつながりの始まりである。
一方、市長の教育論として、小・中学校の義務教育は生涯学習の基礎教育であり、あくまでも教育の最終目標は生涯学習にある、とした。先に述べた、まちは生涯学習の最良の教室であるや、全市博物館構想の「まちづくリビジョン」へと発展させていった。
こういった教育観はおのずといわゆる偏差値教育とか子供の成績の評価を相対的にはかる受験勉強の競争主義とは対極にある。その延長線上の問題として、全国統一学力テストの問題が浮上してくることになる。犬山市は文科省が実施した全国統一学力テストを全国唯一実施しなかった自治体として注目を浴びることになるが、この全国統一して他との比較をし、序列化するという思想を持った学力テストは実施する考えがないということに、犬山の目指してきた教育観が凝縮されている。
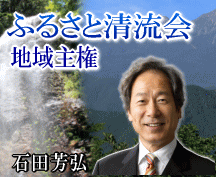
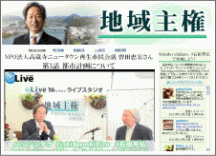
目次
- あれから9年 [動画]
- 三千の話 [動画]
- 静および今井家の話 [動画]
- 子供の時代 [動画]
- 小学生の時代
- 中学・高校生の時代
- 大学生の時代
- 父の家業を継ぎ犬山に戻る [動画]
- 代議士秘書の時代
- 県議選出馬 [動画]
- 愛知県議の時代
- 細川護煕さんとの出会い
- 犬山市長選に出馬
- 犬山市長の時代・地方分権の時代の中で
- 犬山市民病院問題・「さら・さくら」の建設と医師会
- 犬山市のビジョン・河合雅雄さんとの出会い
- 城下町再生物語と成瀬家についての思い出
- 行革の本丸教育改革と民主党との出会い
- 愛知県知事選挙に挑戦
- 東京財団・神野学園その他
- 衆議院議員に当選し、政権交代に参加
- 国会議員として
- 民主主義と議会改革についての提言
- 名古屋市長選挙について
- 補足 子孫に美田を残さず、および日本の祭