アーカイブ: 2011年1月06日
門松めぐり (明治村) (822)
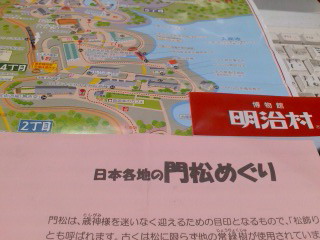
新春の明治村で。
「日本各地の しめ縄めぐり」「日本各地の 門松めぐり」
何気に 慣れっこの正月風景だが、
形や飾り付け方で、ご当地の風習・暮らしが 垣間見えると言う。
(企画書に曰く・・)
「 門松は、歳神様(としがみさま)を 迷い無く迎えるための目印となるもので、「松飾り」とも呼ばれます。
古くは 松に限らず 他の常緑樹が用いられていました。
室町時代になって、「松は千歳(ちとせ)を契り、竹は万代(まんだい)を契る」ということわざから、松と竹が流行するようになりました。
地方によって 竹と松、もしくは松のみなど、種類や形にも 様々あります。
また、家の出入り口の両側に飾る習慣は、明治時代から一般化したといわれており、それ以前は 門だけでなく 庭などに立てる地方が 多くありました。 」



