アーカイブ: 2008年11月
「プリマーテス研究会」-1- 日本モンキーセンター主催
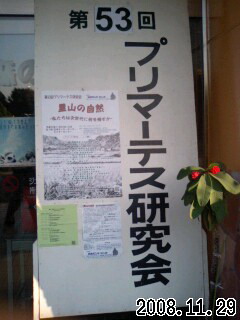
「プリマーテス研究会」第53回シンポジウムに、
11月29、30日 一般参加で出席した。
シンポ会場は日本モンキーセンター・管理棟兼ビジターセンター大講義室。
プリマーテスとは、霊長類(サル)。
1985年日本霊長類学会が設立されるまでは、
この研究会が学会として機能していた。
いまも毎年シンポジウム形式ながら学会のフィールド版として連綿と盛会に続いている。
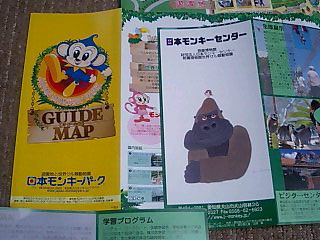
なによりも1956年設立の財団法人日本モンキーセンターと、
その後1967年設立の京都大学霊長類研究所が、
東之宮古墳のとなり、犬山白山平、官林(国有地)の里山に、
地続きで広大な敷地で隣り合っている。
付属博物館、世界サル類動物園、そして名古屋鉄道出資のテーマパーク:ラインパークがつづく。

一世を風靡したテーマパーク:ラインパークは今も根強く子どもたちの人気が高い。
もともと犬山の里山には野生のサル(ニホンサル)が居るうえに、
世界のサルが ン百種類もが 一堂に研究・公開されている。
医学薬学、生物学など学術医薬学研究開発に無くてはならない披検体の、
供給源として重要な機能も果たしている。

犬山・白山・日本モンキーセンターへ

犬山・丸山・白山平へ久し振りに行く、と言っても、いまどきは なかなか通じない。
ラインパークへ行く、と言うなら通ずる。
徳ヶ池越しに 白山:東之宮神社・東之宮古墳からラインパークを見やると、晩秋快晴の紅葉がすすんでいる。
昔ながらのクヌギ・コナラや広葉常緑樹の林が残る。
丸山地区も随分と開発がすすみ、白い壁の建物が増えたなぁ。
ラインパーク駐車場から入り、奥の「日本モンキーセンター・ビジターセンター」前の駐車場へ。
紅葉狩り最盛期の休日で、無風快晴だが来場者の車も少ない。
一日ノータイム千円の料金がきついのかな。


住宅地の奥、おサルさんの居住地近くは、
クヌギ・コナラの落葉樹林が拡がる。


財団法人日本モンキーセンターは、サル(霊長類)の研究、(実験用サルの)供給、社会教育のため、霊長類学の研究センター。
私企業の社会的文化貢献メッセとしても はしりの時代に、
地元名古屋鉄道が財政的スポンサーで設立された。昭和31年(1956)。
いまどきならテーマパークの先端例。
その後昭和42年(1967)、お隣に京都大学霊長類研究所が、
尾張富士山ろく入鹿池畔に、博物館明治村が設立されていく。
.トウカエデの紅葉
トウカエデ。
唐楓と書かれる。中国の東南部、台湾が原産と聞いた。
江戸時代中ごろに 渡来したらしい。
いま、某中核都市の市立美術館長をされているT先生が、
いたくお気に入りの樹であった。
街路樹や公園樹としてよく見かける。
樹高は15㍍くらいになる。
三角形の形をしたもみじ風の葉っぱ。
毎年強めに剪定される街路樹のトウカエデも、
朱色から真っ赤な色に変化しながら 美しく色づいていく。
秋の終わりを告げる紅葉の樹。
工業団地の産業道路に植えられたトウカエデも色づいてきた。

【写真】街路樹の紅葉。トウカエデ。
犬山工業団地 産業道路。 サントリー木曽川工場周辺にて。
犬山インダストリアルパークとも呼ぶ。植栽されて緑化率高い。
ケヤキ 冬支度

道路脇に 一本のケヤキ。
ン十年前までは 10本くらいの仲間とケヤキ林であった。
いまは孤高のひとり立ち。
一年中 小鳥たちの休憩所・・。
落ち葉かき用ネットに10袋分くらいの落ち葉を落とす。
寒空に リンとして たのもしい。
そろりと 冬支度・・。

桑の木 色づく。
五条川畔に 桑畑がある。
このごろは「お蚕さま」を飼う農家は 絶えて久しい。
五条川沿いの羽黒には 大きな製糸工場があり、
尾張、美濃一円の養蚕農家から繭を集めて盛んであった。
時代が変わり、生産緑地指定を受けた田畑地などに、
その名残りを残す。
絹、生糸相場が採算の合う時期時代には、
遠く恵那、中津川、木曾の養蚕農家が切り枝の買い付けに来る。
通学路脇にあるが、
小学生の子たちには 紫色の実を食べる果物の木に見立てられている。

皇帝ダリア 満開

皇帝ダリア。
ただいま 満開。
ご近所の 花愛好家から、
二年前の冬に分けてもらった二節。
多年草だが まだ2年目。
背丈が 4㍍50㌢ほどに成長して花をつけた。
脚立に昇って 写真を撮ったが、
いったいどうやって観賞する花なのだろうか。

「しめ縄作り」講習会・・・・・小弓の庄 平成20年11月23日(日)


小弓の庄平成20年度自主企画。しめ縄作り講習会。
平成20年11月23日(日)に今年も開かれた。

犬山市内のほか近隣市町からも 参加者22名。
“お師匠さん”の地元長老の先生はじめ、小弓の庄企画委員、運営委員も加わって、にぎやかに あるいは黙々とすすむ。
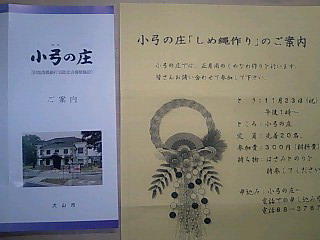
材料は一年がかりで用意。
昨秋もち米から種籾を確保し、種まき、本田植え付けも区別して田植えをする。
真夏の8月、出穂直前に青刈りで刈り取る。
稲わらを 風通しの良いところで陰干しし、気長に乾かす。

わら細工は初めてのひと、去年につづいて二度目のひとなど、
それぞれに おのれの手の器用さ不器用さで 手を撚り合せる。

去年のしめ縄のご利益か、ことし思わぬ大病も無事乗り越えられた話しなど、聞きながら気合が増す・・。
ざっと2時間で、2、3個できあがり!
来年が良い一年でありますように・・。

「羽黒地域 農地・水・環境を守る会」 平成20年11月22日の実践活動
「羽黒地域 農地・水・環境を守る会」平成20年度活動が 11月22日(土)に行なわれた。
犬山市羽黒 堀田・鳳町・稲葉の町内の有志の集まり「昭和会」を中心に、30数名が参加。

今日は、半の木川、伊八サクラ並木一帯の、草刈りやゴミ拾いなど。
日ごろ鍛えしこの身体!
草刈りも ゴミ拾いも サクラ並木の手入れもお手のもの。
段取りの良さ、手際の良さ!すいすいとはかどる・・。

稲刈りを終えた田んぼ一帯は、秋晴れの陽射し。
我らが お山「尾張富士」も穏やかに見守ってくれる。
すっきりとした伊八サクラのもとで、
差し入れのお茶のおいしかったこと!

五条川。晩秋の色。 サクラ冬支度。

五条川。
晩秋の色。 葉を落として 冬支度するサクラ並木。
紅く色づいた葉っぱを落としたサクラたち。
空が広くなった。
この眺め 一等地の脇で、
この秋、分譲住宅開発が進んでいる。

五条川 晩秋の色。 もみじの紅葉

サクラ並木のなかに、 もみじの木がひとつ。
しっかり、色づいている。
五条川 晩秋の色。よし(葦)の群生


五条川。晩秋の色として、目立たないが、
川面いっぱいにまで拡がったヨシ(葦)もある。
5年ほど前に、通水をよくするために
川底に溜まった土砂をブルドーザーで取り除いた。
その後一夏ごとに、ヨシ(葦)が復活し、毎年拡がる。
地下茎はたくましく、ひと夏に5、6㍍以上も伸びて、
2~30㌢ごとに根を下ろす。
水の流れの弱いところがつぎつぎとヨシ原になる。
暑さが厳しい夏ほど 勢いが強まるように思える。
根元には泥が溜まり水の流れをせき止める。
土砂がたまるだけでなく、心無いだれかが放り込んだ家庭ゴミの類いも貯まり異臭を放ち、美観を損ねる面もあるが・・。
とくによく放り込まれる箇所には、五条川沿いの家々の家族がいっしょに川面に入って、ヨシ(葦)の除草作業を何年か置きにやっている。

ヨシ(葦)の群生したところは、
旺盛な成長力が汚泥の中の分解をすすめてくれるようで、
生活汚水が流れ込んでも、ヨシ原がかなり浄化してくれる。
ここを隠れ場所にするのか、巻貝や小さな生き物たちが集まる。
課外学習で小学生らが 生きもの調査に来てくれたりする。
水鳥たちも よく来てくれる。
自分が子どものころ、五条川は、
近所の子どもの、格好の水遊び場所だった・。
やがてどの小学校にも25㍍プールが設置される時代になる。
伊勢湾台風のころに、
サクラ並木の両岸にはフェンス、柵が張られ、
「よいこはここで遊ばない!建設省・○○市」という看板が立ち並んだ。
「泳ぐ」「自分の身体は泳ぎで守る」のが当たり前と思っている。
川の中で水遊びをする中で、泳ぎも覚えた。
しかし その泳ぎは、流れも、うねり・波も無い「プール」という大浴場で、学校の先生に教えてもらう時代へ変わってしまった。
幼な子も子どもも、おとなさえも、
恵の水に親しむ場所から締め出されてしまっていた。
その「よい子はここで遊ばない!」の看板は、このごろとんと見かけなくなった。
この国の河川の管理方針、子育て、教育の時流が右往左往しているからか・・。ビオトープとか、川づくりとかが 声高に唱えられたりして。
五条川は サクラの花見だけでなく、川原で水に親しむところへ復活してやりたい。
心配なことがひとつある・・。
たとえヨシ(葦)の群生しているところでも、生活ゴミを放り込まないで欲しい。
それとびんや缶を投げ込まないで!!
子どもたちが 安全に安心して川原あそびに興じられるようにしてやりたいから・・。
五条川の恵み、水の恵みを 川原の中からも会得してほしいから・・。

五条川 晩秋の色。 サクラ並木

五条川 晩秋の色。 葉を落としたサクラ並木。
上川原歩道橋から上流 尾張富士を望む。
キクイムシに侵入される里山・・・・・・・(どんぐりの木が危ない!)

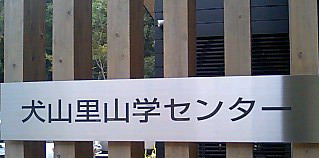
敬道館(犬山市民総合大学)環境学部里山学科。
第3回~いま知る、日本の里山~を受講した。教室は犬山里山学センター学習室。東京大学演習林地域の一角に在る。
講師は東大愛知演習林技術職員で樹木医の澤田晴雄先生。
「カシノナガキクイムシの被害について」
今日は東大演習林に入り込んでのフィールドワークも。

大正から昭和のはじめにかけてのころ、この地方も殖産興国・産業振興の動力資源用と家庭薪炭用に乱伐された。
裸同然に伐り払われ、荒廃した里山を、先人はまず 松などから植林し、復旧させてきた。
ほどよく計画的に、生活用薪炭採取の柴刈り、下草刈りを50年、80年と続けた結果、今日ではコナラや赤松を主体に、落葉広葉樹と常緑広葉樹の里山が拡がっている。
ちょうど尾張パークウエイを車で通るとき、見渡す限りの、緑豊かな里山の景色がその後の姿を見せている。
子どもの頃 冬には山に入って、
毎日毎日、コナラ、ネズコなどを薪用に 柴刈りの手伝いをした里山が、自然林(二次林)に近づいている。
マツクイ虫とその被害は それなりに知っているつもりだった。
北陸、飛騨の山々が、ナラ枯れ病で立ち木が枯れる被害が出ている話も聞いている。
まさか自分たちの廻りの里山で、
「どんぐりの木(コナラ、アベマキ)」が木喰い虫に取り付かれ、
枯れ木の林が拡がっているとは 気づかなかった。
2006年に はじめて確認された。
被害面積が毎年、数倍づつ拡がっている。
ブナ、ミズナラの大木が、その幹に5ミリほどの木喰い虫(カシノナガキクイムシ)が穿孔して繁殖する。
一本のナラの木の幹に、数千から数万匹のキクイムシが梅雨時6、7月に入り込む。
水を吸い上げる細胞の列(導管)を断ち切る具合に、横切ってトンネルを数十㌢以上も掘り進む。
トンネルの壁には、身体に付けて運び込んだ酵母類、ナラ菌類(キノコ)をこすり付けて幼虫の餌に備える。やがて産卵・孵化し成長する。
その数ヶ月後の秋には、
樹高2、30㍍の高木も、葉が枯れ、木が枯れていく。
コナラの幹の根元には、数万匹のキクイムシたちが掘り出した木くずが山盛りに落ちている。


水を吸い上げられず、立ち枯れしたコナラの木から、
翌年初夏には 風に吹かれた成虫が 他の木に飛び移っていくという。
身を任せた風の具合で、数㍍から数キロ㍍先まで飛ぶそうだ。
日本海側の「ナラ枯れ病」が 季節風に乗って徐々に南下し、
コナラ、アベマキの飛騨美濃地帯から、ついに木曽川を越えた。
今のところ、被害が出て3年目の犬山から、ことしは瀬戸・豊田猿投のあたりに散見される。
やがて三河の山々まで拡がると予想される。
なにせ一本の枯れ木から数千匹単位で、風に吹かれて飛び散るのだから人の手に負えない。
これも長ーい目で見れば、生態系、自然の営みであるようだが、なんともやるせない。
樹齢が若く元気なコナラたちは、それでも枯れずに傷口を癒やし、新しい水路(導管)を確保して成長を続けるのが せめてもの救い。
台所や風呂釜が薪焚きの時代には、枝打ち、間伐し株立ちさせていた頃には、木喰い虫も寄り付かなかった。
プロパンガス、オール電化の生活で、里山を人が利活用しなくなった勝手さが、里山の営みと恵みを変えている。
高木のコナラの幹のまわりには、落ちたどんぐりから芽を吹いた、かわいいコナラの若木たちが青空・日当たりがよくなることを待ち焦がれているように顔を上に向けていた。
「がんばれよ。どんぐりの子どもたち!」



