アーカイブ: 2008年11月09日
キクイムシに侵入される里山・・・・・・・(どんぐりの木が危ない!)

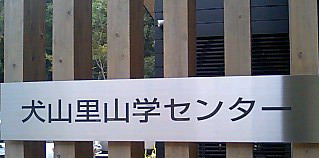
敬道館(犬山市民総合大学)環境学部里山学科。
第3回~いま知る、日本の里山~を受講した。教室は犬山里山学センター学習室。東京大学演習林地域の一角に在る。
講師は東大愛知演習林技術職員で樹木医の澤田晴雄先生。
「カシノナガキクイムシの被害について」
今日は東大演習林に入り込んでのフィールドワークも。

大正から昭和のはじめにかけてのころ、この地方も殖産興国・産業振興の動力資源用と家庭薪炭用に乱伐された。
裸同然に伐り払われ、荒廃した里山を、先人はまず 松などから植林し、復旧させてきた。
ほどよく計画的に、生活用薪炭採取の柴刈り、下草刈りを50年、80年と続けた結果、今日ではコナラや赤松を主体に、落葉広葉樹と常緑広葉樹の里山が拡がっている。
ちょうど尾張パークウエイを車で通るとき、見渡す限りの、緑豊かな里山の景色がその後の姿を見せている。
子どもの頃 冬には山に入って、
毎日毎日、コナラ、ネズコなどを薪用に 柴刈りの手伝いをした里山が、自然林(二次林)に近づいている。
マツクイ虫とその被害は それなりに知っているつもりだった。
北陸、飛騨の山々が、ナラ枯れ病で立ち木が枯れる被害が出ている話も聞いている。
まさか自分たちの廻りの里山で、
「どんぐりの木(コナラ、アベマキ)」が木喰い虫に取り付かれ、
枯れ木の林が拡がっているとは 気づかなかった。
2006年に はじめて確認された。
被害面積が毎年、数倍づつ拡がっている。
ブナ、ミズナラの大木が、その幹に5ミリほどの木喰い虫(カシノナガキクイムシ)が穿孔して繁殖する。
一本のナラの木の幹に、数千から数万匹のキクイムシが梅雨時6、7月に入り込む。
水を吸い上げる細胞の列(導管)を断ち切る具合に、横切ってトンネルを数十㌢以上も掘り進む。
トンネルの壁には、身体に付けて運び込んだ酵母類、ナラ菌類(キノコ)をこすり付けて幼虫の餌に備える。やがて産卵・孵化し成長する。
その数ヶ月後の秋には、
樹高2、30㍍の高木も、葉が枯れ、木が枯れていく。
コナラの幹の根元には、数万匹のキクイムシたちが掘り出した木くずが山盛りに落ちている。


水を吸い上げられず、立ち枯れしたコナラの木から、
翌年初夏には 風に吹かれた成虫が 他の木に飛び移っていくという。
身を任せた風の具合で、数㍍から数キロ㍍先まで飛ぶそうだ。
日本海側の「ナラ枯れ病」が 季節風に乗って徐々に南下し、
コナラ、アベマキの飛騨美濃地帯から、ついに木曽川を越えた。
今のところ、被害が出て3年目の犬山から、ことしは瀬戸・豊田猿投のあたりに散見される。
やがて三河の山々まで拡がると予想される。
なにせ一本の枯れ木から数千匹単位で、風に吹かれて飛び散るのだから人の手に負えない。
これも長ーい目で見れば、生態系、自然の営みであるようだが、なんともやるせない。
樹齢が若く元気なコナラたちは、それでも枯れずに傷口を癒やし、新しい水路(導管)を確保して成長を続けるのが せめてもの救い。
台所や風呂釜が薪焚きの時代には、枝打ち、間伐し株立ちさせていた頃には、木喰い虫も寄り付かなかった。
プロパンガス、オール電化の生活で、里山を人が利活用しなくなった勝手さが、里山の営みと恵みを変えている。
高木のコナラの幹のまわりには、落ちたどんぐりから芽を吹いた、かわいいコナラの若木たちが青空・日当たりがよくなることを待ち焦がれているように顔を上に向けていた。
「がんばれよ。どんぐりの子どもたち!」



