ページ: << 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 283 >>
梅の開花前線 (854)

朝の散歩。
きょうは こっちの路を・・・・。
田んぼのの端に梅畑。
樹齢50年ものの、小梅に花が。
小梅が咲くと、青梅(いわゆる梅干しの梅)が。
そして八重に咲く梅(花梅の類い)がつづく。
このごろ「梅の開花前線」北上・・とは、話題にならないなあ。
なんで、さくら花(ソメイヨシノ)ばかりが、もてはやされるのだろうか。オオシマサクラとエドヒガンの一代交配種のソメイヨシノ。
ソメイヨシノは 花が咲き、実もそれなりに付くが、実を結ぶことはない。花を付け、実を結んで次の世代に発芽することができないソメイヨシノ。
枝の挿し木でしか命をつなげないソメイヨシノ。人の手を借りなければ一代限りで絶滅する花の木が、いままた人を惹きつける。
士農工商の身分制度を下敷きにして、征夷大将軍・幕府統治体制の幕引き近くの江戸時代後期に庭師の手で作り出された「ソメイヨシノ」。挿し木で命をつなぐクローン種。植樹された環境が同じなら、同じ日に開花する園芸種。
河川改修、海岸埋め立ての堤防の踏み固めに、花見の人出の脚数に託す、日本固有の護岸土木工事の智慧の華:ソメイヨシノ。
親政議院内閣制への明治維新への隠し味となり、大東亜共栄圏つくりの、討ちてし已まん・七つボタンはサクラと錨の象徴となったソメイヨシノ。
第三の”開国”の象徴は、花も実もあるウメの花であって欲しい。
ウメの開花前線、ただいま北上中・・・。
花の開花前線 北上!とは、梅の開花前線だったのになあ・・。

気にかかること-5- 「静かにできない大人」 (853)
このまちの小学校のPTAnewsにH会長さんの寄稿文から:
~「日ごろ気にかかることがある」「私たち大人が子どもたちを教育するという立場に在りながら、当たり前のマナーをできていない人(大人)が多いということ、です。」~
~「気にかかること」:そのうち、三つだけ示します・・:
「挨拶をしない大人」「履物を揃えない大人」「静かにしない大人」です。~
**************
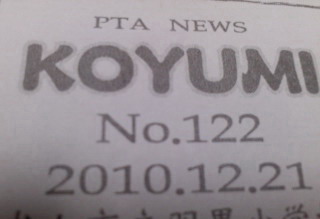
「静かにできない大人」
~「静かにすべき所で 静かにできない大人が多い、ということです」~
~「お通夜などの厳粛な場面でも、最初のうちはコソコソと、そのうちガヤガヤと喋り始める。」~
~また、「子供が騒がしくても 誰一人 注意しようとする大人がいない。」~
~「そんな場面が 最近多いような気がします。」~
***********
人の話しを 最後まで聞いていない。
自分のきょう明日には関係ない、影響しないと思った途端に、
静かにときを過ごす、我慢することがつまらなくなる大人たち。
自分ひとりがその場でほかごとに思いふけることが、
なにか悪さをしている状況に怖くなり、
となりの誰かれなく道連れにして逃げ込もうとする大人たち。
家族で・ご近所で・地域で・学校で・集会で・会社で・・・で、
「これらすらもできない大人たち」が、
「子どもたちを教育する(養育、保育、徳育、知育、体育、食育する)」。
(1)「挨拶をしない」 (挨拶をしない大人)(挨拶を返せない大人)
(2)「履物を揃えない」(判っているのに 揃えない大人)
(3)「静かにしない」 (判っているのに、我慢できない大人)
まず自分から、 そして、わが子から、わが家から始めよう。
「挨拶を自分が先にする」(相手が自発的に 挨拶を返せるまで)
「その都度、その場で履物を揃える」
(整理する、とは、次にすぐ使える状態に揃えておくこと)
「静かにする。」 (他人を巻き込まない)(他人と比較しない)
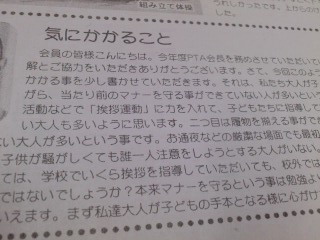
気にかかること-4- 「履物を揃えないおとな」 (852)
このまちの小学校のPTAnewsにH会長さんの寄稿文から:
~「日ごろ気にかかることがある」「私たち大人が子どもたちを教育するという立場に在りながら、当たり前のマナーをできていない人(大人)が多いということ、です。」~
~「気にかかること」:そのうち、三つだけ示します・・:
「挨拶をしない大人」「履物を揃えない大人」「静かにしない大人」です。~
**************
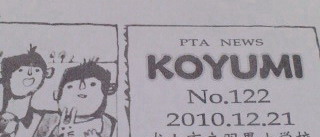
「履物を 揃えることができない」。
保育園、幼稚園では、入園式の日の初めての日から、
「履物を揃える」「下駄箱へ履物を入れる」。
この躾けが“いの一番の約束ごと”
ご縁の濃い保育士さんのボヤキを思い出す・・:
「お箸の持ち方、使い方が身に付いていない」
「着衣帽子のひもが結べない・きれいに解けない」
「鉛筆の持ち方、運びが身に付いていない」、
そして「履物を 揃えることができない」。
地域の活動のひとつに、御神楽保存会活動がある。
秋の大祭が近づくと、毎晩集会場で笛太鼓の練習会をする。
子ども会を中心に小中学生の子たちも参加してくれる。
子たちは 履物を揃えて下駄箱に並べる。
大人たちの何人かは ザラ板前やら、土間へ脱いだまま上がる。
企業の健康診断に出向いたときの、眼の付け所の一つ:
「正門の周囲、玄関周りの整理整頓、清潔を見よ」
「意識して手洗い所を借用し、湯沸し場で水を飲め」
腑に落ちなかったら、「食堂・休憩所を診よ」
帰りは「裏門・勝手口から出て、外周用水路の中を診よ」と。
むかしから言われる ことば:
小中学校の担任の家庭訪問は、玄関とトイレ借用で半分判る。
集合時刻に厳しい子か。給食のあいさつ・箸運び・好き嫌いは。
親子の絆と育児、家族の掟・躾け、ご近所との付き合い。
すべては「生きる力」、群れで生きる「掟と役割り献身を身体で学習する力」をつけるため。
「(返事はできても)挨拶ができない子どもと 大人」
「(ひとりで履けても)履物を揃えることができない子どもと 大人」
・・・「子どもは地域の宝もの」「子どもは未来からの預かりもの」
「それができない親・大人」。そんな「親に育てた祖父母・大人」。
他人のせいではない。
いますぐ、大人が実行し、当たり前の暮らしに しよう・・。
・・「子どもは 親の背中を見て 育つ」。

気にかかること-3- 「挨拶ができない大人-2-」 (851)
野良仕事をする。車も通らない狭い旧道沿いだ。
駅に近く、朝夕に限らず、往来が多い。
中学校への通学路で、生徒たちが毎日通る。
道端に近いところで野良仕事をしていると、登下校中で、おしゃべりに夢中の子たちも、絶妙の距離で、 「お早うございます」「こんにちは!」と声をかけてくれる。
この子たちは 気持ちよく育っているなあ、と思っていたが、どうやらそうばかりではないようだ。
野良仕事、道端で一服する。
通りがかる大人たちに、こちらから「こんにちは」と声をかける。 顔なじみの人はすぐに声が通う。 勤め帰り、どこかへお出かけ風の大人たちからは、“無視される”のが、実はほとんどだ。
朝夕に、飼い犬の散歩の人、ウォーキングでやってくる人。
「こんにちは」と声かけしても、“無視する”大人(中には中学生らしい子も)が実はほとんどだ。
PTAのH会長さんの言葉通り、「挨拶をしない大人」「挨拶ができない大人」「挨拶されるのを迷惑顔ですり抜ける大人」「挨拶されても他人事で無視する大人」が、実は十中八九が日常化している。
うれしいこともある。幼な子の手を引いた親・祖父母たちは、もれなくにこやかに挨拶が交わせる。
その子たちが中学を卒業すると、「挨拶ができない人」になっていってしまう。
そもそも「挨拶は、こころのふれあいのまくら言葉」。
「挨拶を返さない若者」「挨拶をしようとしない“ひとの道”を通る大人」として成人する地域に、PTA会長のHさんは強い危機感を持っておられる。
「挨拶は、ひとの道の一丁目一番地」だと思う。
ことばを持たない生き物ですら、仲間を眼で耳で認めたら、もれなくリアクションするのになあ。
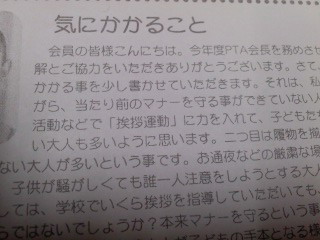
気にかかること-2- 「挨拶ができない大人」 (850)
このまちの小学校のPTAnewsにH会長さんの寄稿文から:
~「日ごろ気にかかることがある」「私たち大人が子どもたちを教育するという立場に在りながら、当たり前のマナーをできていない人(大人)が多いということ、です。」~
~ 一つ目は「挨拶です」。
~ 学校や社会活動などで「挨拶運動」に力を入れて、子どもたちに指導していただいていますが、最近は挨拶ができない大人が多いように思います。学校でいくら挨拶を指導していただいても、校外では(※筆者註※ 家庭や、ご近所では)挨拶ができない。~
~ これは私たち大人が、挨拶ができていないからではないでしょうか。~
朝 起きたら、家族同士が、まず一人づつ、「お早う!」
そのとき、お互いの顔を見合わせて「お早う!」
出かけるときは、顔を見合わせて、「行ってきます!」
帰ってきたら、顔を見合わせて、「ただいま!」
食事は極力揃って食べる。
時間がずれたら、だれかが食卓に着いて「孤食」には しない。
「いただきます」「ごちそうさま」
・・・これが、三世代で夕食を囲むわが家の毎日・・。
このごろ孫たちが毎日電車で通うようになってきた。
ご近所の老友から「あんたのとこの孫たちは、いつも先に声掛けてくれて、挨拶してくる。気分がいいよ」と聞かされる。
・・・実は、こちらこそ「おかげさまで!」と お返しする・・。
(内心「うれしくて、ありがたくて」。こころで小躍りしている)
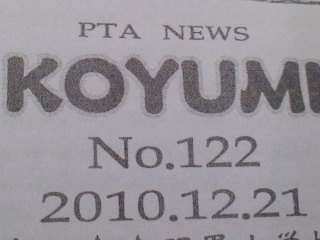
<< 1 ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... 283 >>


