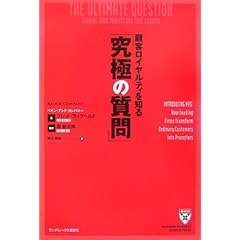ページ: << 1 ... 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 >>
五条川 サクラ満開


五条川 桜並木も いま満開。
正面にお山(尾張富士)の景勝地。
彼岸桜が満開になったは、つい3、4日前。
今年はソメイヨシノが追い重なるように開花して、2,3日後には どちらも揃って満開期を迎えた。
彼岸桜の「葉サクラ期」に、ソメイヨシノの「開花、満開期」が追いかけるのが、この地の五条川の歳時記・春であった。
だが、ことしは陽気がちょっとちがう・・。


通りがかりに、たたずんでしばらく見とれたが、寒かったこと。
明日は4月。 もう4月だ。
間もなく、かわいい保育園児、にぎやかな児童たちが、新入学・新学期で、このサクラ並木を通園通学する。
サクラ咲く。春本番。


【写真】犬山羽黒・五条川の桜並木。
通学路小弓橋から上流(上)と下流(下)。
顧客満足CSに”究極の一冊”! 顧客ロイヤルテイを知る『究極の質問』
小売業界サービス業界に限らず、「顧客満足」こそが第一だと言われ続けて久しい。
お客さまが満足していただいたかどうかを、販売者・サービス提供者が、覆面調査員が膨大なチェック項目を採点したものや、アンケート・はがきで顧客に尋ねて返される回答を、集計分析し数値化して、その良否・是非を知る。
これが顧客満足CSの教科書もの、ノウハウものの多くであったように思える。
果たして、「これでお客さまが増え、リピート率も向上し、これからも増加・向上させられると確信できる」と言えるだろうか。
この一抹の不安、納得しきれない気持ちから、一気に目覚めさせてくれる、指針を示してくれるのが、『・・究極の質問』であった。(フレッド・ライクヘルド著、鈴木泰雄訳、ランダムハウス講談社2006刊)
・・手法としては顧客満足度調査の実施風であるが、「たったひとつの質問を発し、お客さまの回答・意思表示を得ること、これで顧客のロイヤルテイを知る」。
この四半世紀もの間、作る側・出し手の論理、提供者の理屈で、お客さまと向き合い、自分の都合を”売り込み”、引き渡したらそれで終わりとしてきた現場。
この現場の自己中心的・自己満足と、経営の志の浅さが、目からウロコどころか、一瞬にして瓦解し、その中から新しい源泉、若芽を見つけることになっていく・・。
書評を評するものの言葉はさておき、自分の目と心眼で捉えてください、とお勧めできる一冊。
梅満開 ただ今 見ごろ!

梅 満開 ただ今 見ごろ!
わが家の梅も ただ今 満開。
うぐいすは このごろ姿を見せてくれないが、
きょうは 黄色い帽子 かわいいお散歩隊がやってきた。

さあさあ みんな たのしかったね
なにが いたかな なにを 見つけたかな

元気な羽黒っ子 お山(尾張富士)も見てござる
きょうは ポカポカ陽気 思い切り 咲き競う

3月2日 野呂塚 供養祭、粛々と。
3月2日(日)犬山羽黒は八幡林近くの「野呂助左衛門碑」で、ことしの供養祭が催された。
犬山羽黒の地元のひとたちが、野呂家ご一族を招いて野呂公顕彰会として、毎年3月17日の命日ごろ開催されている。

野呂公顕彰会の文書に趣旨がある・・
「天正12(1584)年3月(17日)小牧長久手八幡林合戦に戦死の野呂助左衛門宗長、助三朗親子ならびに西軍、東軍の無名武士の諸霊を供養し」「後世に語り伝え保存、顕彰し」「地域の歴史文化発展に」・・・と。
三寒四温の春先だが、本日は風もおさまり青空が抜ける快晴。
犬山市一円の史跡同好の多くの方の参列参拝もあり、賑々しくも粛々と・・・。
神職のご祈祷、供養につづき、琵琶・尺八演奏の奉納も。
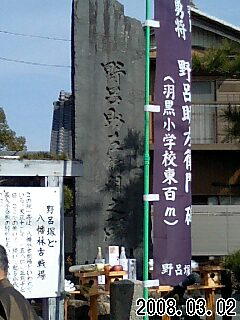
余談だが、八幡林の合戦、長久手の戦いで決着が着かなかった翌4月には、秀吉に従い参戦していた山内一豊が、羽黒の森川屋敷の番となり羽黒城の修築を為し、羽黒の陣の長となる。
奇しくも羽黒は、山内一豊の数奇なご縁の地でもある。
一豊の母・法秀院は羽黒城主梶原元左衛門の娘で、その母の在所の地で、一豊は はじめて陣を任される。
その後一豊は同年9月、近江長浜に5000石を与えられ名実ともに「城持ち」となっていく。
まもなく5月には「梶原景時公顕彰会」の「梶原忌」がご当地近くの菩提寺・興禅寺でことしも行われる。

野呂塚碑の西側、いまは電車道をはさんで、八幡林、八幡神社へとつづく。
「小牧・長久手の戦い」の緒戦となった八幡林合戦地の西端。
いまは羽黒小学校(昭和22年ごろに新制羽黒中学校建設)敷地になった松林の一帯のなごり。

八幡神社参拝の折り、かたわらの「戦役紀念碑」に気がついた。
子どもの頃には ここで遊んでいても気づかなかったけれど。
碑文を見て驚いた・・。
明治41年8月 羽黒村尚武会 建設とある!。
まつられているのは、明治21年戦没者と凱旋者。そして明治37、8年戦没者で、名を聞き及んでいる知り合いのご先祖様の名も見つけた。総勢百名余もが記されている・・。
きょうは 400余年前と、100余年前の武勇者と出会う供養と顕彰の一日・・・。
よい品よい考え・・トヨタ経営憲法
機会を得て、トヨタ自動車工場視察研修会に参加してきた。
トヨタの工場のあちらこちらで、「よい品よい考え」の緑色カンバンが目につく。創業者豊田佐吉のことばであったと記憶する。
1950(S25)年トヨタ自工社長に就任した石田退三は、後年“これがトヨタの経営憲法である”と説いたと聞く。よい品物をつくれ。自動車は耐久力が大事だから、耐久力のあるクルマをつくれ。値段が高くてはなんにもならないから、コストダウンを真剣に考えていこう、とも。
創業者豊田佐吉はまた、いまでいう電脳自動化機械も始めた。
機械そのものに善し悪しを判断させる装置を組み込んで「自働化」するもの。
ニンベンのついた自働化の生産方式だと説明を受け、組み立てラインに混流生産で、前後が車種も色もさまざまな車が(見学した工場では2ラインで日当たり1300台ペースで)作られる現場に、圧倒される。
「必要なものを必要なときに必要なだけつくる」生産哲学が、1937(S12)年自動車を創業した豊田喜一郎の提唱であり、大野耐一時代に構築完成するトヨタ生産方式は、日々の絶え間ないカイゼンがきょうもつづく。その進化のど真ん中を通り抜けた一日だった。
かって30年も前だがIBMワトソン研究所での研修会で受けた「THINK,THINK,THINK考える」にも通ずる衝撃波に押されて、きょうはトヨタの「よい品よい考え」を考えさせられる。

※トヨタ会館エントランスホールで出迎えてくれたトヨタ・パートナーロボット