カテゴリ: 畑仕事はカルチャー
ページ: << 1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 267 >>
田んぼ 初氷 張る

師走に入って 冷え込みがきびしい。
里山雑木林脇の田んぼに 初氷が張った。
クヌギや雑木が いちだんと色づく。

屋根より高いイルミネーション


ご近所。
師走の愉しみ。
屋根より高いイルミネーション。
毎年この時季愉しませて もらっている。
もう十何年にもなろうか・・。
まいとし少しづつ すこしづつ増えてきて とうとう満艦飾に。
ことしは何が増えたかなあ、と 眺める愉しみをいただいている。
いつも ありがとう。


長良川河口堰
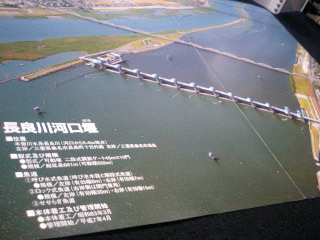
所用があって 長良川河口堰へ出向いた。
「アクアプラザながら」として、見学者案内・学習施設もある。
年中無休、入館料無料とはうれしい。(年末年始5日間は休館)
平成7年1995年4月から供用管理開始から 10余年。
水害、塩害のない環境づくりを目指している。
平成10年1998年4月からは、淡水化された取水口から、
長良導水(知多半島水道用水)、中勢水道(北伊勢工業用水と津市周辺水道用水)の取水、供用も始まっている。
河口堰のおかげで・・、というおかげさま認識が語り継がれるようになるには、まだまだ時間がかかることだろう。
長良川河口堰の建設には 是々非々あったし、これからもあるかもしれない。
1755年薩摩藩負担で木曾三川の分流を目指したした宝暦治水。
1887年明治20年から1912年明治45年にかけて明治政府直轄での、木曾三川完全分流工事(明治改修)。
100年ぐらいのスパンで、見てみたい。

水資源機構・長良川河口堰管理所の玄関ホール、壁面いっぱいに、
巨大な航空写真が掲げられている。
木曾三川流域航空写真:ジオラマを眺めながら、
木曾三川の壮大さ、恵みの大きさに圧倒される。
メソポタミア文明、チグリス・ユーフラティス川文明、ナイル川文明、黄河文明などの 栄枯盛衰の変転を思う。
年々歳々気候変動の少ない気象条件・水の恵みと、
「樹を切ったら苗木を植える」「木の文化の民族」で、
ン千年経っても山紫水明を保つ国土と国民。
「里山の文化」(植林と除伐間伐)、
「里地・田んぼの文化」(年中通水、田んぼは貯水池)、
(土壌は生きものにも耕してもらう文化)、
用水路、上下水道、洪水氾濫抑制など 先人の知恵と努力。
有史以来3000年、5000千年と、
ほぼ同じ民族が 同じ場所に定住し続けている流域。
日本列島には当たり前のように、たくさんの流域がある。
ユーラシア、アフリカ、南北アメリカ大陸を見回しても、
亜熱帯・温帯ゾーンでは
よそに例の少ない、特異な文明文化を持つ 定住・永住民族。
母なる大地、木曾三川バンザイ! ありがとう木曽川!!
帰りの車中 気が付けば、「木曾節」を口ずさんでいた・・。

プリマーテス研究会-5- 里山・田んぼこそ資源国


江戸時代終期から1960年ごろまで100年間、
現国内で、衣食をまかなってきた耕作地。
(化学肥料・薬品の過度な施業をせず、水田の乾田化を抑制すれば)田んぼの生きものの力で分解に助けられ、稲作できる土壌を維持できる。
稲作を中心に、ン百年先まで4~5000万人分の食糧を自給できる、とも。
*************
里山、田んぼは、その下流域の生きものとヒトと経済の貯水池・浄化槽である。
さて、「水資源・食糧源としての森林・田んぼの維持」、「せめて5000万人分の自給食糧の国内生産」は、どの世代が どう分担するのか。
**************
この50年間、水(海)に流し、地中に隠した廃棄物。
未処理で流した洗剤・工業薬品、過度な化成肥料・殺虫剤、・・。
とりわけ生物生態系が分解・循環し切れない量の廃棄物。
その大半は原材料として、国外から輸入した原油系(CO2、樹脂類)と鉱物・・。
この最終処理は、だれが負担するのか。
どの世代が、どう負担するのか。
ヒトは 動植物・生物に「いま現時点の、自分にとって不都合・不利益なこと」を、他者に送りつける。 次世代に残そうとしている・・。
ヒトは 地上と地下から得た資源を また土に還すまでの後処理コストを購買価格に含めて買おうとしなかった。
作るヒト、売るヒトは売りっぱなし。資源回収・再利用・土に還す最終処理を、自らはすることなく、コストも充分払わないで他者に任せっぱなしにしてきた。
ヒトは 次世代のヒトと生きものに、大きな負荷を先送りしつづけている・・。
************
研究会の帰り道、ムラの田んぼに しばし見とれた。
稲刈りを終え、稲株の並ぶ田んぼ。
江戸時代後期、明治時代前期は、人口4000万人ほどが、
里山・里地、雑木林・田んぼと、よく折り合って暮らしていたなぁ・・。
「うさぎ追いし、かの山。 こぶな釣りし、この川。
・・・
山は青き ふるさと。 水は清きふるさと」

primates研究会-4- 生涯孫無し率50%!?
プリマーテス(霊長類)研究者が年一回シンポジウム形式の学会を、犬山市の財団法人日本モンキーセンターで開催する。
霊長類の頂点にいるヒトの生存生活環境として、里山の自然・次世代に何を残すかを、主テーマにこのところすすんでいる。
一般参加で 二日間同席して、たくさんの刺激を受けた。
************
ヒトは、ピーク90億人規模にもなりそうなヒトは、どれだけ勝者のヒトとして生存できるのか。
富を蓄えるヒトとそうでないヒトが 地球上でどのように共存できるのか・・。
************
日本の人口推移は 「人口転換」がはげしい、という。
①少子高齢化。 出生から成人までの死亡が激減し、だれもが高度医療を受けて寿命が延びる「疫学的転換」が進む。
生存曲線の老化遅延、というのだそうな。
②多産多死から多産少死へ。そして少産少死へ。
種の保存と 種の生存(何世代も先へ生き延びる)の摂理として、
減り過ぎそうだと一気に増やし、共倒れする危険が迫ると急速に自己調整する。
さまざまな生きものに「出生転換」が見られるという。
日本でも4人出産から 2人出産へ。
1930年ごろ出生率4.72人。1970年ごろ2.13人。
そして2010年ごろは おそらく出生率1.29人前後。
************
やがて 50歳未婚率が24%へ、 生涯子供なし率が38%へ、
生涯孫なし率が50%へという時代が すぐそこまで来ている、とも。
一人当たり保育、養育、教育の負担。親だけが負担か、親世代のヒトも負担か。
いろいろな事象は「自らの生き方(生存)(生殖)が 合理的に選択できる」「ヒトの社会・経済の」時代がなせるもの、というが・・。
************
<< 1 ... 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 ... 267 >>


