ページ: << 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 283 >>
ひとは なぜ 旅をするか
「 ひとは なぜ 山に登るか 」
・・・・・ 「 そこに 山が 在るから 」
「 ひとは なぜ 学ぶか 」
・・・・・ 「 ひとは 生きるために 学ぶ 」
「 ひとは なぜ 生きるか 」
・・・・・ 「 ひとは 学ぶために 生きる 」
いま、ちょっぴり、旅に出たい気分。
「 ひとは なぜ 旅をするか 」
・・・・・ 「 そこに ひとが 居るから 」
そう、ひとは 旅に出る。
いろいろ見聞体験するだろうが、
出会ったひとの 生きざまを 学ぶ。
ひとには 出会わなかったとしても、
書き留めたり、だれかに見聞体験を 語りたがる。
・・・・・ 旅は 人生の教師である、とか。
「 ひとは 旅を する 」「 そこに ひとが 居るから 」
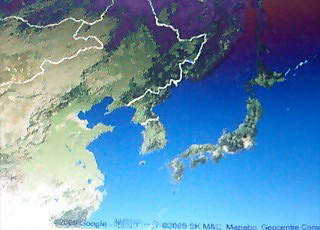
「田んぼの生きもの図鑑」-水生昆虫編- -2-
いま 手もとにポケット版64ページの小冊子が2冊ある。
『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅰ コウチュウ目・カメムシ目-
『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅱ トンボ目-
田んぼの学校に参加する子たちや家族の方たちにも喜んで利用していただけそうな優れものの小図鑑だ。
難しい漢字にはルビもあるが、小学校高学年クラスの説明文。
親子いっしょに使う場面を想定しているのかな。
ゲンゴロウ類、ガムシ類、カメムシ類など「田んぼとそのまわりの水の中にいる生きもの」を、手軽に見比べられるのもうれしい。
トンボ編ではトンボの一生の解説もわかりやすい。
収録されたトンボの数が60種もある。そんなにこの国の田んぼの周りにはいるのか!とびっくり。
ことしは生物多様性のCOP10名古屋会議の年。
ひとりでも多くの子どもたちが手にして、親しんでもらいたい。

「田んぼの生きもの図鑑」-水生昆虫編- -1-
いま 手もとにポケット版64ページの小冊子が2冊ある。
『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅰ コウチュウ目・カメムシ目-
『 田んぼの生きもの図鑑 』-水生昆虫編 Ⅱ トンボ目-
3月に社団法人農村環境整備センターから、贈呈を受けたもの。
「田んぼの学校」活動の普及などでご縁があって いただいた。
(この図鑑は宝くじの普及宣伝事業として作成されたもの)
水生昆虫編-Ⅰ- 2009.3.25.発行。
水生昆虫編-Ⅱ- 2010.2.26.発行
企画・発行 社団法人 農村環境整備センター
編集・制作 社団法人 農山漁村文化協会
編集協力 財団法人 自然環境研究センター
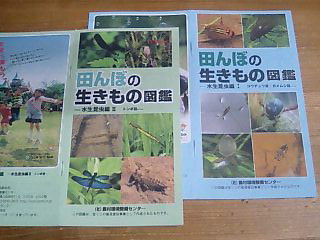
学力とは 生きる力である。 -4 yoi-
学力を身に付けるため、人は学ぶ。
学力とは、知識がある、知識を増やすことだけではない。
学力とは、「生きる力」があるということ。
「逆境をはねかえして、最後まで生き抜く力」である。
学力=知識ととらえると、知識の有無、知識の量で測って〇×をつけて終わり。 〇の数の多さで点数化して、序列をつけて一喜一憂したりしがちとなる。
「ひとと比較するためだけの学力テスト」は、有害とさえなる危険性が かなり高い。
自分の学び具合を確かめるためのテストとだけ考えろと言っても、
新しい未知の世界への挑戦、あらかじめ用意された解答も無いものへの挑戦する意欲をかきたてられるキッカケにならない危険性が高いのが、あの“学力テスト騒動”だった。
平成の教育の世界では、「序列をつけられると安心する」「学歴を着けました、という生活保険に加入する」、その幻想が霧消しはじめている。
*******
学ぶのは生きるため、生きる力をつけるために学び続けるのだ。
学力があるということは、
生きる力がある、
未知のことへ挑戦する力がある、
逆境をはねかえす力がある、
最後まで生き抜く力を身につけていること。

学ぶために生きる。 -3yoi-
[ 遇うたびに、なにか こころに おみやげをくれる人から聞いた話。]
そもそも なんのために勉強するのか。
いつまで勉強するのか。
ゴールは死ぬまで。 生涯 学習をするため、ひとは勉強する。
頭(脳)は 使えば使うほど、活性化する。
“生涯学習する”とは、
学ぶために生きる。 そして 生きるために学ぶのだ、という。
******
勉強が楽しい。 「学ぶことは 愉しいことだ」
よ~し、勉強するぞ!と、
こころに火を点ける教師こそが、卓越した教師の姿なのだろう。

<< 1 ... 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 ... 283 >>


